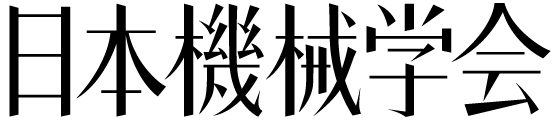No.201 「Fukushima50」と「黒部の太陽」
2021年度編修理事 越塚誠一[東京大学 教授]
JSME談話室「き・か・い」は、気軽な話題を集めて提供するコラム欄です。本会理事が交代で一年間を通して執筆します。

2021年度編修理事 越塚誠一[東京大学 教授]
「Fukushima50」と「黒部の太陽」
2011年3月の東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所(1F)事故から10年が経過したが、1F事故からの復興は途上であり、未だに広範囲の帰還困難区域が残されている。Fukushima50とは、1F事故において最も困難な時期に現場に残った吉田所長を含む約50名の方々を指す[1]。2020年3月のちょうど新型コロナの感染拡大の時期に映画「Fukushima50」が封切られ、その後DVDの発売やテレビでの放映もあり、筆者の専門に関係しているため興味深く見た。また、昨今の新型コロナ拡大で筆者も家にいる時間が長く、他にもいろいろな映画を家で見た。その中で、1968年公開の映画「黒部の太陽」は「Fukushima50」と似ている。「黒部の太陽」で描かれているのは、黒部川第4発電所の黒部ダムを建設するためのトンネル掘削工事で、工事の途中で破砕帯にぶつかり、多量の出水を乗り越えてトンネル貫通までこぎつけるというものである。これと比較しながら「Fukushima50」の感想を述べたい。
「Fukushima50」では1Fの所長を渡辺謙が、1・2号機の運転制御室の当直長を佐藤浩市が、刻々と悪化する状況の中で懸命に事故に対処する姿を演じている。一方の「黒部の太陽」では、トンネル工事を発注した関西電力の事務所次長を三船敏郎が、現場で掘削を担当する親方の二代目を石原裕次郎が好演している。どちらの映画も主人公が二人いて、困難な中で最善を尽くそうと努力する技術者を描いている。ただし、全般的に「Fukushima50」の方が情緒的に作られているように感じた。「黒部の太陽」にあるような技術的な説明は少ない。
1F事故の最も過酷な時は、2号機の格納容器の圧力が上昇した3/15の朝である。爆発音がして、その直後に2号機のサプチャンの圧力が0MPaになり、発電所対策本部ではこれを2号機の格納容器が大規模に破損したものと考え、一部の者を残して約10km南に位置する東京電力福島第二原子力発電所等に避難させる。この時に1Fに残った者がFukushima50と呼ばれることになる。政府事故調では現場対処に関して詳細な調査が行なわれた[2]。これによると、2号機の格納容器の破損は誤認識であった。そもそも格納容器はドライウェルとウェットウェル(サプチャンと同じ)から構成され、それぞれに圧力計が付いているが、3/14の夜からウェットウェルの圧力計は不自然に低い値を示し始め、ドライウェルの圧力計が引き続き高い値を示していたことから、ウェットウェルの圧力計の故障が強く疑われる。また、圧力計は絶対圧を示すものであり、大気圧は約0.1MPaで、0MPaは真空を意味する。格納容器が大規模に破損したのであれば大気圧の0.1MPaを示すはずである。実際には針は0MPaよりさらに下がるダウンスケールであったと考えられ、ここからも圧力計の故障が疑われる。さらに、爆発音は6時10分ごろに発生しているが、ウェットウェル圧力のダウンスケールは6時2分の時点で測定されており、爆発音の後に圧力が急低下したわけではない。爆発音は2号機の格納容器が破損したためではなく、3号機で発生した水素が4号機に流れて、4号機の原子炉建屋で爆発したために生じたものである。2号機では水素爆発は発生しなかった。この誤認識は、3/11の地震発生から既に4日も経過して現場に疲れがあったことと、ちょうど2号機の格納容器の破損を心配していたことから、やむを得ないことだったかもしれない。しかしながら、爆発音と格納容器圧力に因果関係があると誤認識してしまったことは、技術に携わる者に対してはむしろ反省点として伝えられるべきことだと考える。
米国原子力学会の事故報告書[3]では、Fukushima50を日本独特の文化が表れているとし、否定的な見解を示している。”VI.D. Cultural Perspectives”から引用すると、”For the Japanese, the Fukushima Fifty were a symbol of national resolve and willingness to sacrifice to protect the nation. (中略) In contrast, in the Western media the Fukushima Fifty were a symbol of the desperate measures required – a shocking sign of how desperate things had become.”と記述されており、「ハラキリ」「神風特攻隊」に重ねているのであろう。確かに、原作[1]ではそのような観点も書かれている。しかし、文化論で事故を評価すると、異なる文化の国においては教訓にならないし、そもそもdesperateであったとの米国原子力学会の認識は間違っていると思う。実際、特例省令による被曝限度250mSvを超える放射線を受けた者は6名いたが、総じて1Fの事故対処では被曝限度が常に意識され、守られていた。例えば、1号機の格納容器ベントでは、2つめの弁の手動による開操作は高線量のために途中で断念している。ここで無理をしなかったことは、技術的には評価されるべきあろう。工事で多数の犠牲者を出した「黒部の太陽」の時代よりも進歩していると感じる。
筆者は技術者に向けた別の「Fukushima50」が必要ではないかと考える。そこでは、困難な状況の中で現場がどのような覚悟を持っていたかだけでなく、現場がいったい技術的に何を考え、何をしていたのかを追いかけ、解説を加え、その当時の誤認識や間違った対処なども冷静に記述して、後の技術者の教訓とすることができるようなものである。
[1] 門田隆将, 死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日, PHP研究所 (2012) [2] 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会「最終報告」(2012) [3] American Nuclear Society, “FUKUSHIMA DAIICHI: ANS Committee Report” (2012)