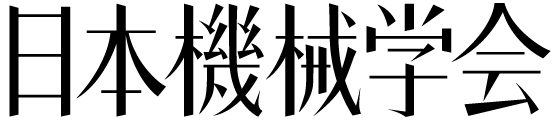東北学生会 第55回学生員卒業研究発表講演会
U R L https://www.jsme.or.jp/conference/tohoku-gakusei55/
企 画 東北学生会
開催日 2025年3月7日(金)
会 場 発表講演(オンサイト)、zoomによる発表も認める場合あり
(八戸工業大学(青森県八戸市大字妙字大開88-1))
講演申込受付開始日 2024年11月23日(土)
講演申込締切日 2024年12月20日(金)
講演申込み資格について
(1)講演申込を行うためには,発表者は日本機械学会に所属する会員である必要があります.講演申込される際には,発表者の日本機械学会の会員番号を必ず記入し,学会員であることを明らかにしてください.
(2)講演申込みを行う時点で日本機械学会への入会申請中の場合,講演申込ページの会員番号欄には「仮登録番号」を記入してください.そして,日本機械学会の会員番号を入手後,講演申込ページから申込番号とパスワードを使ってログインし,仮登録番号を会員番号に修正してください.
(3)講演会当日においても日本機械学会の会員ではない場合,本講演会での発表はできません.
原稿提出開始日 2025年1月13日(月)
原稿提出締切日 2025年2月7日(金)
問合せ先 日本機械学会第55回東北学生会卒業研究発表講演会事務局/太田勝/
電話: 0184−27−2191 E-mail: ohta+gak55@hi-tech.ac.jp
講演申込ページ U R L: https://www.jsme.or.jp/conference/tohoku-gakusei55/doc/mousikomi.html
日本機械学会第55回東北学生会卒業研究発表講演会事務局(担当:太田 勝)
第11回日韓機械学会合同・熱流体国際会議/The Eleventh JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference
詳細は後日
関西支部 第396回講習会「実務者のための振動基礎と制振・制御技術」
詳細は後日
関西支部 ステップアップ・セミナー2024「技術者によるAI活用と関わり方」
関西支部 学生のための企業技術発表会
東北地区特別講演会 「国境を越えたロボティクス: 日本とヨーロッパにおけるラテンアメリカ人のロボット工学への貢献」
No.24-140 東北地区特別講演会
「国境を越えたロボティクス: 日本とヨーロッパにおけるラテンアメリカ人のロボット工学への貢献」
URL https://jsmetctohoku.github.io/
企画 ロボティクス・メカトロニクス部門 第1地区技術委員会
開催日 2024年11月19日(火) 10:00~12:00
会場 東北大学大学院工学研究科機械・知能系共同棟6階会議室
(仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-01)
http://www.eng.tohoku.ac.jp/map/?menu=campus&area=a01&build=15
プログラム
(1) 10:00~11:00
「Robotics Technologies and their Benchmarking at International Robotics Competitions」
講師:Gustavo Garcia(立命館大学 准教授)
International robotics competitions bring together the research community to solve real-world, current problems such as drilling in aircraft manufacturing (Airbus Shopfloor Challenge), warehouse automation (Amazon Robotics Challenge), and convenience store automation (Future Convenience Store Challenge). In this talk, I will discuss our approach to these competitions and describe the technical difficulties, design philosophy, development, lessons learned, and remaining challenges. In particular, I will talk about the Future Convenience Store Challenge, whose goal is to create an autonomous robot to remove expired products and place new products on convenience store shelves, including temporarily stopping work when a customer requires a product from the shelf operated by the robot, and the decision-making process behind this system, as well as our latest research on decision-making using Large Language Models.
(2) 11:00~12:00
「Challenges towards Industry 5.0 in controlled environment plant production systems with high proportion of local renewable energy:
From system integration to optimization of techno-economical intelligent control systems」
講師:Jorge Solis(カールスタード大学准教授/早稲田大学非常勤研究員)
In this lecture, Prof. Solis will present a new project that deals with the development of intelligent control systems for greenhouse lighting with a high proportion of local renewable energy. The project will develop an intelligent control system to optimize the operation of lighting systems in greenhouses with a high proportion of local renewable energy using adaptive control methods, Artificial Intelligence (AI) algorithms and optimization of built-in lighting control. Through this, lighting systems will be optimized, energy consumption will be minimized and the lighting system will be adapted to be able to handle a larger amount of local renewable energy production.
参加費 無料
申込方法 申し込みは不要です.当日お気軽にお越しください.
問合わせ先 Salazar Luces Jose Victorio / 電話(022)795-6942
Email: j.salazar@srd.mech.tohoku.ac.jp
第11回JSME先端生産技術に関する国際会議(LEM21)
主催: 日本機械学会(生産加工・工作機械部門) 共催: 日本機械学会(生産システム部門) 開催日:2025年12月1日-2025年12月4日 目 的: 生産加工・工作機械部門の国際的活動のひとつである,The 11th International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st Century (LEM21/先端生産技術に関する国際会議) を,2025年12月1日から4日までの日程で,沖縄県糸満市にて開催することとなりました.本会議は1997年にスタートして以来20年を迎え,第11回を数えるものです.本会議では,13のオーガナイズドセッションに加えて,3件(予定)のプレナリーレクチャーを設けます.文化交流が盛んな糸満市ならではの会場で,ものづくりに関わる様々な分野の技術者,研究者,経営者が一堂に会し,最新技術の議論や知識の共有が期待されます.多くの方々のご参加を心よりお待ちしております. 主要トピックス(オーガナイズドセッション): OS01: Advanced machine tools OS02: Mechatronics and robotics-integrated manufacturing OS03: Digital manufacturing (CAD, CAM) OS04: Smart manufacturing (IoT, AI, CPPS) OS05: Cutting technology OS06: Grinding technology OS07: Finishing technology OS08: Forming technology OS09: Electro-physical and chemical processes OS10: Laser processing OS11: Additive manufacturing OS12: Surface, tribology and structuring technologies OS13: Nano/Micro measurement and intelligent instruments 発表された全論文中の優れた論文に対しては,Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing(JAMDSM, published by JSME)への特集号への掲載推薦,ならびにInternational Journal of Automation Technology(IJAT, published by Fuji Technology Press)特集号への掲載推薦が行われます.各ジャーナルでは査読プロセスを経て掲載の可否が決定されます. 会場: 糸満市観光文化交流拠点施設 シャボン玉石けん くくる糸満 https://www.kukuru-itomancity.jp/ 開催概要・参加登録について: 下記HPよりご確認ください. https://scoop-japan.com/kaigi/lem21_2025/ 問い合わせ先 LEM21実行委員会 lem21_mmt[at]jsme.or.jp ※[at]を@に変換してください. 申し込み締め切り 2025年3月31日
東北支部および東北支部シニア会 2024年度施設見学会
企 画:日本機械学会 東北支部・東北支部シニア会
開催日:2024年11月8日(金)
概 要:
東北地域においては,東日本大震災および原子力発電所事故災害の影響を受けながらも,IoTやAIの発展に伴うDXおよび脱炭素社会構築のためのGXなど大きな変革の中にあり,それぞれの県において特徴あるものづくり企業が集積され,変革へのチャレンジが行われているところです.
このたび,日本機械学会東北支部および支部シニア会の共催により,東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)様の大きなご協力のもとに,利府町にある「JR東日本新幹線総合車両センター」の施設見学会を開催させていただきます.東北新幹線,上越新幹線,北陸(長野)新幹線,さらに山形新幹線,秋田新幹線と多様な車両を運行するシステムは,我が国の高度な鉄道技術とその保守技術により成り立っていると考えています.JR東日本様がめざす「究極の安全」を第一に,新幹線運行を中核として支える新幹線総合車両センターの施設見学は,我が国における高度なものづくり基盤技術を知る貴重な機会と思いますので,東北支部会員,シニア会員,そして学生会の皆さまのご参加をお待ちしております.
なお,JR東日本様には,特別にお願いして見学をお認めいただいておりますことを報告させていただき,感謝申し上げます.また,見学については,最大数40名での訪問となることから,少人数のグループを形成しての見学となりますことを予めご承知おきください.
JR東日本:東日本旅客鉄道株式会社 https://www.jreast.co.jp/
JR東日本 新幹線総合車両センター(宮城県宮城郡利府町)
スケジュール:
12:50 ~ 13:35 仙台駅から貸切バスにて移動,仙台駅東口集合,新幹線総合車両センターへ
13:40 ~ 14:05 挨拶,会社・車両センター概要説明VTR,見学準備(会議室にて)
14:05 ~ 15:05 車両センター工場視察(1班20名とし,班に分かれて逆順にて見学)
(所要時間:55分程度を想定)
15:05 ~ 15:15 講堂にて合流,休憩
15:15 ~ 15:50 技術開発プレゼン(内容検討中),意見交換会
15:55 ~ 16:40 仙台駅へ貸切バスにて移動,エントランス発,仙台駅東口へ
17:00 ~ 懇親会(仙台駅周辺にて,参加希望者のみ)
定 員:先着40名(東北支部会員限定,学生会員を含む)
申込締切日:2024年10月25日(金)(ただし満員になり次第締め切り)
会 場:JR東日本新幹線総合車両センター(宮城県宮城郡利府町)
参加登録費:無料(仙台駅集合までの交通費,懇親会費は自己負担)
申し込み先:
E-mailにて「東北支部シニア会2024年度見学会」申込みと題記し,
(1)参加者氏名,(2)会員番号,(3)現役の場合は所属,
(4)連絡先(電話,E-mail),
(5)懇親会参加希望の有無を記入の上お申し込みください.
申込先・問合せ先
担当 東北支部 岡本 E-mail:jsme.tohoku@gmail.com
申込締め切り
2024年10月25日(金)予定
実験力学の先端技術に関する国際会議(ATEM27)
詳細は後日
VE/VRを用いた設計・開発・ものづくりの新しい検討手法の紹介
【開催日時】
2025年1月7日(火) 13:00~17:35
【開催形態】
ハイブリッド開催(オンラインはZoom利用,対面会場は日本機械学会会議室)
〒162-0814 東京都新宿区新小川町4番1号 KDX飯田橋スクエア2階
https://www.jsme.or.jp/about/about-jsme/access/
◆参加費のご入金が確認出来た方には,開催1日前を目途に,ZoomミーティングIDとパスワード・当日用資料について,お申し込み時のメールアドレス宛へご連絡します.
【協賛】
自動車技術会,精密工学会,日本設計工学会,日本計算工学会,日本シミュレーション学会
【趣旨】
Industry 4.0,IoT等のDigitalを用いたビジネスの動きや新しい開発/ものづくりの話題が毎日聞こえてくる昨今です.それに関連として「距離/時間/要素を同一の場」で共有検討できる共通の3Dデータ環境としてVE(Virtual Engineering)が注目を集め加速展開しております.2020年5月に経産省より発表された“ものづくり白書”に「我が国の製造業では3Dによる設計が未だに普及しておらずバーチャル・エンジニアリングの体制が整っていない.不確実性が高まり製造業のダイナミック・ケイパビリティの重要性が増している中で,このバーチャル・エンジニアリング環境の遅れは我が国製造業のアキレス腱となりかねないと言っても過言ではない」と記述されています.また本年6月には経済産業省とNEDOから製造事業者各社が直面する経営課題の解決に向けて経営・業務変革課題の特定を起点としてデジタルソリューションを適用・導入する企画・構想設計に重点を置いた「スマートマニュファクチャリング構築ガイドライン」を共同で策定し発表しています.(https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628004/20240628004.html)
このように設計・開発・ものづくりの新しい手法に対してデジタルソリューションの活用による変革へ緊急と危機感を持った動きが活発になってきました.
日本機械学会 設計工学システム(D&S)部門では2013年以来,今年度で12回目となりましたが,CAD/CAM/CAE/PLM/Data流を駆使する“VEとVR(Virtual Reality)の動向と活用検討”を講習会で紹介して来ました. 今年度は,これに加えData活用とスムーズなData流を構築するための標準化技術についての動向も示したい.
参考:日本機械学会技術と社会部門ニュースレターより
世界の図面変革に遅れる日本の状況と「空気を読む」習慣https://www.jsme.or.jp/tsd/news/newsletter47/47no05.pdf
日立総研レポートより
バーチャルエンジニアリングのもたらす産業革新
https://www.hitachi-hri.com/journal/__icsFiles/afieldfile/2022/11/17/Vol17-2-3.pdf
【プログラム】
司会:理化学研究所 内田孝尚
1. 13:00~13:55 「VR からメタバースへ」
東京大学名誉教授 廣瀬通孝
内容:
メタバースをはじめとするリアルとバーチャルの境界領域に存在する一連の技術群が今後ひきおこすであろう社会変革は,いわゆるインダストリー4.0 の概念よりもずっと広汎なものである.本講演では メタバースの現状と将来についてまとめた上で,機械工学を中心とする産業構造の在り方や方向性について,具体的事例を交えて考えてみたい.
休憩 13:55~14:00
2. 14:00~14:50 「バーチャル環境における空間認知と生体反応」
東海大学 情報理工学部 情報メディア学科 教授 濱本和彦
内容:
人が無意識に行っている環境内での行動,例えば「手を伸ばしてモノを掴む」「上体をひねって隙間を通る」「足を上げて障害物を避ける」などは,環境と身体の相互作用で生じる「生態学的認識(または認知)」と呼ばれる.
デジタルツインをトレーニングなどに活用する際にはバーチャル環境内で現実環境と同じ「生態学的認識」が得られることが重要である.
本講演では,バーチャル環境と現実環境における生態学的認識の違い,それを同等とするための考え方について報告する.併せてVR酔いに代表されるバーチャル環境内での生体反応についても述べる.
休憩 14:50~14:55
3. 14:55~15:45 「プレス部品の量産におけるSmart ManufacturingとSmart Manufacturingを活かすためのVEの重要性」
オートフォームジャパン株式会社 代表取締役社長 鈴木 渉
内容:
自動車業界は100年に1度の変革期と言われる.このような大きな変化は脅威として捉えられることが多いが,新たな成長の機会としなければ生き残ることができない.競争に打ち勝つためには他社に先んじて変化に挑戦し競争力を獲得する必要がある.その中で新しい技術としてのAI技術の進歩には目を見張るものがあり,プレス領域でも活用検討が進んでいる.プレス部品の量産不具合解決に向けたAIの活用の取組みとAI活用のための前準備としてのVEの重要性に関して説明する.
4. 15:45~16:15 「データドリブン・マニュファクチャリング時代の進行と日本の課題」
理化学研究所 研究嘱託 内田孝尚
内容:
新しい開発/ものづくりの動きは今から20年ほど前,大きく舵を切っていたと思われます.その動きは全世界的に,3D/Digital/Virtualを用いた新しい設計/開発/ものづくり環境への移行に繋りました.営業,ユーザーも含めた「距離/時間/要素を同一の場」としたVE(Virtual Engineering)環境の加速展開が進み,ポテンシャルの高い製品アウトプットが始まった.と同時にそのデジタルデータを用いたビジネスの変革が拡がっている.そのビジネスの変革も含め、世界のVEの動きを説明したい.
休憩 16:15~16:20
5. 16:20~17:20 「機械設計のDXを推進するエンジニアリングデータの国際標準」
ISO/TC184/SC4国内対策委員長 株式会社エリジオン代表取締役 相馬淳人
内容:
機械設計で3次元CADが利用されるようになって久しい.CADの3次元形状は,三面図と比較して圧倒的に視認性が良く,CAEやCAMなどのソフトウェアによる業務変革の道も開けた.一方で,形状以外の寸法,公差,材質,加工方法等々,もともと図面にまとめて記載されていた情報がそれぞれ別に管理されるため,情報の分断,不整合が発生しており,製品開発プロセスのDX推進において大きな阻害要因となっている.
この問題の解決に向けて,国内外でどのような取り組みがなされているか,国際規格の話題を中心に解説する.
6. 17:20~17:35 「本日のWrap Up」
理化学研究所 研究嘱託 内田孝尚
【定員】
現地15名,オンライン定員無し.
現地参加の希望は先着順とさせていただきます.
【参加費(税込)】
正員・特別員(行事参加割引コード利用)・協賛団体一般10,000円,
正員(継続特典)・大学院生の会員(正員)・学生員・協賛団体学生5,000円,
会員外15,000円,一般学生7,500円.
◆学生員から正員資格へ変更された方は,卒業後3年間,学生員価格にて講習会にご参加いただけます.お申し込みの際,「正員(継続特典)」を選択し,卒業年と卒業された学校名を「通信欄」にご記入ください.
◆大学院生の会員(正員)の方は「学生員」を選択し,「通信欄」に所属大学院名,課程・学年をご記入ください.
◆特別員(法人会員)で参加される場合,「行事参加料割引コード」のご利用で参加費は正員価格となります.お申し込みの際,「特別員」を選択し,「会員番号」に「行事参加料割引コード」(xxxxxxx-xxxx)をご記入下さい.
◆「特別員行事参加無料券」のご利用で,参加費は無料となります.「特別員(無料券利用)」としてお申込みの上,以下の担当職員まで「行事参加無料券(原本)」をご郵送ください.
〒162-0814 東京都新宿区新小川町4番1号 KDX飯田橋スクエア2階
一般社団法人日本機械学会 設計工学・システム部門担当 秋山宛
◆協賛団体会員の方は「協賛団体一般」「協賛団体学生」を選択し,「会員番号」に協賛団体会員番号,「通信欄」に協賛団体名をご記入ください.
【教材】
上記参加費には教材1部(DL版)代金を含みます.なお教材(DL版)のみご希望の方は,行事終了後,1部につき会員2,000円,会員外(協賛団体会員含む)3,000円(いずれも税込み価格)にて頒布いたします.ご希望される方は1/14以降に下記ページよりご購入下さい.
https://www.jsme.or.jp/publication/event-pub/
【申込締切】
12月24日(火)
【申込方法及び注意事項】
Payventより受付
URL: https://app.payvent.net/embedded_forms/show/6704d3c7cf19cf277aef34c6
■聴講料は,12月24日(火)までにご入金をお願いします.
■聴講料のお支払いには,クレジットカード(Apple pay,Google pay含む)・銀行振込のいずれかがお使いいただけます.
■銀行振込の際の振込手数料は各自でご負担いただきます.予めご了承ください.また,振込先の口座は申し込みごとに異なり,他の申し込みとまとめてのお支払いは出来かねます.
■銀行振込でのお支払期限は,原則としてお申し込みから3日以内です.ご入金が確認出来ない場合,こちらでキャンセル処理をさせていただきますのでご了承ください.
■お申込内容は,Payventより配信されるお申し込み完了メールからご確認いただけます.メールが届かない場合は「payvent.net」からのメールを許可するように受信設定をお願いします.
■原則として,決済後はキャンセルのお申し出がありましても返金できませんのでご注意願います.本ページからのお申し込みについては,集会事業申込規約にご同意いただいたものとみなします.
【領収書】
■領収書のお宛名には参加者の氏名が自動で記載されます.ご所属先を宛名に追加する場合は申込フォームの”領収書のお宛名”欄に記載をお願い致します.(こちらに氏名を入力しますと,宛名に氏名が重複しますのでご注意ください)
■領収書はPayventからのお支払い完了メールに記載されているURLよりダウンロードいただけます.
【問い合わせ先】
設計工学・システム部門担当 秋山 宗一郎/TEL:03-4335-7613/E-mail: akiyama@jsme.or.jp
関東支部 第31期総会・講演会
【開催日】2025年3月3日(月)~4日(火)
【会場】埼玉大学
【主催】(一社)日本機械学会
【後援】埼玉大学
【総会・講演会ホームページ】
https://www.jsme.or.jp/conference/ktconf25/page.html
【特別セッション(SS)】
01 学生のための企業技術発表会
【オーガナイズドセッション(OS)】
01 機械工学が支援する微細加工技術(医療・バイオから半導体・MEMS・NEMS)
02 最新IOT技術、統合型生成AIやAIコミュニケーション技術
03 ロボティクス、メカトロニクス
【一般セッション(GS)】
機械工学に関わる21カテゴリーを用意しています.
申し込み状況に応じて,セッション数とセッション名を変更する可能性があります.
また,申込内容によって,上記OSに繰り入れる場合があります.
【発表資格】
日本機械学会個人会員(正員,学生員)の方のみ発表いただけます.
会員外で発表を希望される方は,
https://www.jsme.or.jp/member/register-application/individual-member/
から入会手続きをお済ませの上,会員番号取得後,講演申し込みを行ってください.
*入会フォーム入力から入会完了までの期間はおおよそ1週間をご予定下さい.
*会員登録は入金確認後となります。入金から確認に数日程度かかりますのでご注意下さい.
会員番号欄に記入がないものは発表対象となりませんのでご注意ください.
研究発表(登壇)は一人につき一件のみとさせていただきます.
【講演申込締切】
2024年11月5日(火)
申込締切後は講演題目(副題を含む)と著者名(連名者を含む)の変更はできませんのでご注意ください.
【講演申込方法】
総会・講演会ホームページ https://www.jsme.or.jp/conference/ktconf25/page.html
よりお申込み下さい.申込手続き完了後,採択通知をE-mailにてお送りします.
なお,若手優秀講演フェロー賞および若手優秀講演表彰の審査のために,
登壇者の会員番号と生年月日を必ず入力して下さい.
【原稿提出締切】
2025年1月10日(金)
【原稿準備および提出方法】
原稿は,講演会ホームページ掲載の「投稿原稿執筆要領」に従って作成して下さい.
https://www.jsme.or.jp/conference/ktconf25/page_6.html
関東支部 第31期総会(2025年3月3日開催)
【問い合わせ先】
日本機械学会関東支部第31期総会・講演会実行委員会
〒162-0814 東京都新宿区新小川町4番1号 KDX飯田橋スクエア2階
日本機械学会 関東支部
E-mail: ktconf25@jsme.or.jp
見学会「川崎市・浮島処理センターにおける資源循環および大規模太陽光発電施設」
■企画:日本機械学会 環境工学部門 第3技術委員会
■開催日:2024年11月22日(金)12:50~16:00
■見学先:浮島処理センター(神奈川県川崎市川崎区浮島町509−1)
■趣旨:この度、川崎市・浮島処理センターの見学会を企画致しました。浮島処理センターは、最新のごみ焼却施設、資源化処理施設、特殊焼却施設を集合させた総合施設です。バイオマス発電設備を含む施設全般を見学します。さらには併設されている大規模太陽光発電施設を見学します。
■見学行程(予定):
- かわさきエコ暮らし未来館(https://eco-miraikan.jp/index.html)
- 浮島メガソーラー展望スペース,
- 浮島メガソーラー構内
- 浮島処理センター(https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/288-12-1-0-0-0-0-0-0-0.html)
- 資源化処理施設(https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013405.html)

■当日スケジュール:
- かわさきエコ暮らし未来館 1階休憩スペース 12:50集合(時間厳守)
- 【見学開始】 13:00
- 【見学終了】 16:00
- 現地解散
■参加資格:本会名誉員・正員・学生員
■募集人数:現地参加のみ 先着30名様まで
■参加費(施設利用料とツアー代金):無料
※集合場所までの往復交通費は各自負担となります。
■申込方法:
URL : https://jsme24-138.peatix.com
※上記Peatixからお申込みください.
※Peatixコメント欄およびメッセージ機能で連絡いただいても返信できかねますので,ご不明点は下記の問合せ先にご連絡ください.
■申込締切:2024 年11月20日(水)
■備考:
- 荒天時は中止・変更となる場合があります。実施日前日~当日にメールにて状況報告いたしますので、見学会取りまとめ(奥村・吉田)からの連絡にご注意ください。
- お申込時に入力いただいた氏名・所属・役職の情報を見学先に提出することはありません。
- 施設内に喫煙所及び自動販売機の設置はありません。
- 浮島センター内に食事をする場所はありませんので、食事は事前にお済ませください。
- 移動が多いため、動きやすい服装・履物でご参加下さい。
- 当日発熱のある方や体調のすぐれない方は参加をご遠慮ください。
- 止むを得ず参加できなくなった場合には、速やかに下記の問い合わせ先(2)までご連絡下さい。
第37回バイオエンジニアリング講演会
講演会ホームページ https://www.jsme.or.jp/conference/bioconf25/index.html
主 催:日本機械学会バイオエンジニアリング部門
開催日:2025年5月24日(土)〜25日(日)
会 場:慶應義塾大学日吉キャンパス(神奈川県横浜市)
URL: https://www.keio.ac.jp/ja/maps/hiyoshi.html
協賛(予定):計測自動制御学会、硬組織再生生物学会、電気学会、電子情報通信学会、日本医工学治療学会、日本実験力学会、日本生活支援工学会、日本生体医工学会、ライフサポート学会
開催趣旨:本講演会は,1988年度より交互に開催されていたバイオメカニクスカンファレンスとバイオエンジニアリングシンポジウムを1997年度に統一して始まりまし た.その後のバイオエンジニアリングの発展はめざましく,医療・福祉やバイオ産業のみならず,メカノバイオロジーなどの基礎科学にも大きく貢献することが期待されています.今回の講演会では,前回の第36 回バイオエンジニアリング講演会を踏襲し,シンポジウム形式のOS(Organized Session)を基本とし,一般口演のGS(General Session)も併用したプログラムを企画する予定です.また,例年同様に一般演題は基本的にポスターセッションで発表していただきます.バイオエンジニアリング部門に関連する皆さまが一堂に会し,日ごろの研究成果を発表するとともに,有意義な議論・情報交換ができる場を提供いたします.
申込先:第37回バイオエンジニアリング部門講演会HP
https://www.jsme.or.jp/conference/bioconf25/index.html
講演申込方法:上記の講演会HPからお申し込み下さい.
講演資格について:本講演会で発表頂くには,本会個人会員(正員,学生員)であるか,協賛団体(*)の会員である必要がございます.会員資格をお持ちでない方は,この機会にぜひご入会をご検討下さい.会員資格は申込み時に必要です。
(*)相互性(研究発表に関し本会会員が協賛・後援団体において同等の扱いを受ける)が確認できる団体に限ります.
<参考URL>
https://www.jsme.or.jp/conference-presentation/
<入会手続き>
https://www.jsme.or.jp/member/register-application/individual-member/
※講演申込時に,会員番号の入力が必要です.会員外の方は講演申込期限の前日までに入会(入会費の払込み)を完了してからお申し込み下さい(ご入金後の翌営業日に会員番号が発行されます).
問合せ先:第37回バイオエンジニアリング講演会 事務局
E-mail:bioconf25[at]jsme.or.jp ([at]を@に変えてください)
関東学生会 第64回学生員卒業研究発表講演会
URL https://www.jsme.or.jp/kt/sotsuken/64thGakusei.html
企画 関東支部
開催日 2025年3月3日(月)
(関東支部第31期総会・講演会は2025年3月3日(月)に併催,4日(火)に単独開催となります)
会場 埼玉大学
講演申込締切日 2024年11月5日(火).講演申込は学生会員に限ります.講演申込時には正式な会員番号が必要になりますので,講演申込締切日迄に間に合うよう入会手続き(会費支払まで)を完了するようお願いいたします.入会手続き方法は https://www.jsme.or.jp/member/register-application/individual-memberをご参照下さい.
原稿提出締切日 2025年1月10日(金)
募集要項
(1) 登壇者は,日本機械学会学生員で,かつ学部4年生(高専5年生および専攻科2年生を含む)の卒業予定者とし,卒業研究を発表していただきます(大学院生不可).
(2) 登壇者は学生員に限ります.講演申込までに学会入会手続きを完了していない場合には,講演申込ができませんのでご注意下さい.講演申込時には正式な会員番号が必要です.
(3) 講演申込と学会入会手続きは異なりますので,それぞれにお申し込み下さい.
(4) 講演時間は1題目あたり10分,討論は5分,計15分とします.
★(5) 原稿は,A4判1段組で2~5頁とします.ファイルサイズは2MB(メガバイト)以内としてください.
★(6) 原稿の作成については,「日本機械学会関東支部 関東学生会 卒業研究発表に際して」
( https://www.jsme.or.jp/kt/sotsuken/sotsuken.html )を必ずご覧下さい.
(7) 会員校の役員(教員等)に,開催要項,講演原稿の書き方,入会申込みなどの詳細資料を送付してあります.会員校ではない大学等に所属している学生でも講演申込みは可能です.
(8) 登壇者には司会をお願いする場合があります.
講演申込方法
・ 関東支部WEBサイト( https://www.jsme.or.jp/kt/sotsuken/64thGakusei.html )から講演者自身によりお申し込み下さい.
・ 講演のお申し込みサイトの「ステップ3著者・共著者情報」画面において,「学部4年」,または「高専5年」のように講演者の学年を必ず入力して下さい.
・ 講演のお申し込みサイトの「ステップ3著者・共著者情報」画面において,指導教員情報を必ず入力して下さい.
Best Presentation Award
関東学生会および関東支部では,すばらしい口頭発表を行った学生員に対してBest Presentation Awardを贈賞いたします.
参加登録費 登壇者(2025年2月16日までの参加登録費):2 000円(ダウンロード版予稿集を含む)(不課税)
登壇者(2025年2月17日以降の参加登録費):3 000円(ダウンロード版予稿集を含む)(不課税)
聴講者:無料(ダウンロード版予稿集の提供なし)
なお,登壇者に限り,併催の関東支部第31期講演会の聴講は無料となります.
懇親会費 学生員/会員外学生(課税) 2 000円(2025年2月16日までの懇親会費)、4 000円(2025年2月17日以降の懇親会費)
正員/会員外(課税) 5 000円(2025年2月16日までの懇親会費)、10 000円(2025年2月17日以降の懇親会費)
★予稿集・講演論文集
〇予稿集の発行について
予稿集は, Web上での配布となります(冊子やUSB、CD-ROMでの配布は行われませんのでご注意ください).予稿集の販売は行われません.
〇講演論文集の発行について
講演論文集には,当日未発表の原稿,1ページ原稿,掲載を希望しない原稿は含まれませんのでご注意ください.なお,講演論文集ダウンロード版をご希望の方に販売致します.(後日販売となります.当日の販売はございませんのでご注意ください.) 講演論文集には,関東支部第31期総会・講演会の内容も含みます.価格は,会員3,000円,会員外5,000円(いずれも税,送料込)です.希望される方は下記問合せ先へお申込み下さい.
問合せ先 日本機械学会関東支部 関東学生会 電話(03)4335-7620/E-mail: kt-staff@jsme.or.jp
令和6年度 ⽇本機械学会 中国四国⽀部 徳島地区 特別講演会
開催⽇ 2024年11⽉22⽇(⾦) 13:30〜15:40
会 場 徳島⼤学 常三島キャンパス ⼯業会館1F 多⽬的室
講演1(13:30〜14:30)
■ 講師:島津製作所 分析計測事業部 ラボメカニクスビジネスユニット 花房 信博 ⽒
■ 講演タイトル:パンデミックへの挑戦
〜新型コロナウイルス検出試薬及び遺伝⼦解析装置AutoAmpの開発〜
- 講演概要:
2020 年1⽉中旬に国内最初の新型コロナウイルス感染者が報告され,同年3⽉には第1波の流⾏
が起こった.当時、核酸増幅検査の体制は⼗分ではなく,体制強化が求められていた.このような
状況の中,弊社では同年4⽉に迅速簡便な遺伝⼦検出試薬を,また同年11⽉に全⾃動PCR検査
装置を発売した.国難に向けたこれらのスピード開発や精度管理等の取り組みについて紹介する.
休憩(14:30〜14:40)
講演2(14:40〜15:40)
■ 講師:徳島⼤学⼤学院 社会産業理⼯学研究部 機械科学系 ⼤⽯ 昌嗣 ⽒
■ 講演タイトル:リチウムイオン⼆次電池⾼容量正極材料のX線を⽤いた電⼦・結晶構造解析
■ 講演概要:
次世代リチウムイオン⼆次電池の⾼容量正極材料として,リチウム過剰系層状酸化物が注⽬され
ている.⾼容量発現メカニズムについて,X線を⽤いた分析法による解析結果を紹介する.
参加費:無料
定員:100名(オンサイト:50名,オンライン:50名) (ハイブリッド開催)
申込み⽅法:下記のMicrosoft Formsサイトからお申込み下さい
https://forms.office.com/r/pe5vSUTZL2
申込み〆切:2024年11⽉8⽇(⾦)
問合せ先:太⽥光浩(徳島⼤学⼤学院 社会産業理⼯学研究部 機械科学系)
E-mail:m-ohta@tokushima-u.ac.jp Phone:088‒656‒7366
もう一度学ぶ機械材料学(金属材料の基礎)
2024/12/11追記 申込者の方に当日のURLと配布資料を案内しました(Payvent経由)
【企 画 】機械材料・材料加工部門
【開催日】2024年12月17日(火)10:00~17:30
【会場】 オンライン(ZOOM)
※ミーティングIDとパスワードについてのご連絡は,開催2日前を目途にPayvent経由にてご案内予定です
【協賛(予定)】日本金属学会,軽金属学会,日本鉄鋼協会,自動車技術会,精密工学会,日本材料学会,日本塑性加工学会,日本鋳造工学会,粉体粉末冶金協会,溶接学会,一般社団法人日本航空宇宙学会,日本実験力学会
【趣旨】
「ものづくり」の現場でご活躍の若手・中堅技術者、あるいは新入社員でこれから現場に入る方を対象に,「ものづくり」の素材となる機械材料の基礎から理解できる講習会です.
機械材料として広範囲で用いられる金属材料を中心に平易な解説を行います.
【講師】 工学院大学 工学部 准教授
博士(工学) 柳迫 徹郎 氏
【プログラム】
導入:「機械材料とは」 金属,セラミックス,高分子材料および複合材料(10分)
1. 金属材料の基礎(50分)
1.1 金属結合
1.2 金属材料の特性
1.3 金属材料の強化方法
2. 平衡状態図の読み方,使い方(50分)
2.1 平衡状態図の基礎
2.2 全率固溶型
2.3 共晶型
(昼食休憩:)
3. 鉄鋼材料の特性とその応用(80分)
3.1 Fe-C状態図と標準組織
3.2 鋼の熱処理
3.3 合金鋼とその特性、特殊用途鋼とその特性、ステンレス鋼とその特性
4.非鉄鋼材料の特性とその応用(80分)
4.1 アルミニウム合金とその特性
4.2 チタン合金とその特性
4.3 銅合金とその特性
5. セラミックスおよび複合材料(50分)
5.1 セラミックスの強度および強化機構
5.2 複合材料の基礎(複合則)
6. 構造材料の評価方法(50分)
6.1 引張試験,曲げ試験
6.2 硬さ試験
7.. まとめ及び技術相談
【定員】80名,
申込み先着順により定員になり次第締め切ります.
【聴講料】
聴講料は下記となります
会員資格 受講料(税込み)
正員・特別員・協賛団体会員 20,000円
学生員・正員(学生員から正員への継続特典対象者)・協賛団体学生員 5, 000円
会員外 35,000円
一般学生 15,000円
【教材】
教材のみの販売予定はありません。
当日参加者のみに、当日用の資料をご案内する予定です。
ダウンロード用のURLをミーティングIDと併せて2日前にお送りいたします.
※当日配布資料有無については今後変更の可能性ございます
【申込方法】
お申込みは こちら
※【お申込の際の注意事項】をご一読ただきお申込みください
【申込・入金締切】
2024年12月6日(金)厳守
【お申込の際の注意事項】
・参加費については,必ず上記期日までに決済をお願いします.決済が確認出来た方には視聴用のURLをお送りいたします.
・聴講料のお支払いには,クレジットカード(Apple pay、Google pay含む)・銀行振込のいずれかがお使いいただけます.
・銀行振込の際の振込手数料は,各自でご負担いただきます。予めご了承ください。また、振込先の口座は申し込みごとに異なり、他の申し込みとまとめてのお支払いは出来かねます
・銀行振込でのお支払期限は,原則としてお申し込みから3日以内です。ご入金が確認出来ない場合、こちらでキャンセル処理をさせていただきますのでご了承ください.
(申し込み かつ 入金期限は12月6日まで)
・お申込内容は,Payventより配信されるお申し込み完了メールからご確認いただけます。メールが届かない場合は,「payvent.net」からのメールを許可するように受信設定をお願いします.
・原則として,お支払い完了後はキャンセルのお申し出があってもご返金できませんので何卒ご了承ください.
本ページからのお申し込みについては,集会事業申込規約にご同意いただいたものとみなします.
・学生員から正員資格へ移行された方は,卒業後3年間,本会講習会へは学生員価格で参加可能です.申込先フォームの会員資格は「正員(学生員から正員への継続特典対象者)」を選択し,通信欄に卒業年と卒業された学校名をご入力ください.
・協賛学協会会員の方は「協賛団体一般」「協賛団体学生」を選択し、会員番号欄に所属団体の会員番号を、通信欄には協賛団体名をご記入ください。
・特別員の資格(正員扱い)で行事に参加される場合,聴講料は正員の価格となります.下記申込先フォームの会員資格は「特別員 行事参加料割引コード利用」を選択し,「会員番号」に「行事参加料割引コード」(xxxxxxx-xxxx)をご記入下さい.
・「特別員行事参加無料券」を利用される場合,聴講料は無料となります.予め「特別員行事参加無料券(原本)」をご用意の上,「特別員 行事参加無料券利用」としてお申込みください.「行事参加無料券(原本)」を一番したの以下問合せ先にご郵送ください.
【問合せ先】
〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番1号KDX飯田橋スクエア2階
一般社団法人 日本機械学会 近藤
TEL: 03-4335-7610
E-mail: m.kondo[※]jsme.or.jp
実践・最適設計
【開催日時】
2024年12月16日(月) 13:10~17:10 ,17日(火) 13:10~17:10
【開催形態】
オンライン開催(Zoom ミーティングを利用)
◆参加費のご入金が確認出来た方には,開催3日前を目途に,ZoomミーティングIDとパスワード・当日用資料について,お申し込み時のメールアドレス宛へご連絡します.
【協賛】
日本設計工学会,日本計算工学会,塑性加工学会,日本船舶海洋工学会,精密工学会,自動車技術会,日本航空宇宙学会
【趣旨】
設計生産分野に限らず,多くの工学分野で最適設計法の活用は大きく進んでおり,金属AM(Additive Manufacturing)による製造技術開発も可能になってきています.最適設計法の実務への活用を考える上で,多様な分野における活用事例を示すことで,さらなる最適設計法の普及と発展が期待できます.昨年度は主として最適設計法の数理に焦点を当て講習会を開催しましたが,今年度は最適設計法の実践に焦点を当てた講習会を企画しました.日本の最適設計をけん引する研究者を講師に招き,様々な工学分野における最適設計法の実践例を紹介していただきます.
【プログラム】
12月16日(月)
1. 13:10-14:00(質疑応答14:00-14:10)
「アディティブマニュファクチュアリングにおける最適設計の活用」
早稲田大学基幹理工学部 教授 竹澤 晃弘
近年,積層造形(3Dプリンティング)技術が著しく発展し,ものづくりでの活用法が活発に検討されている.中でも,従来の製造法では難しい複雑な形状でも製造できることから,優れた構造を創出する手段として構造最適化が注目を集めている.本講義では,積層造形を活用する際に有益となるという観点から,構造最適化の基礎知識について積層造形技術自体と併せて解説を行う.
休憩(15分)
2. 14:25-15:15(質疑応答15:15-15:25)
「情報学と力学の融合に基づく新しいトポロジー最適化の方法」
京都大学大学院工学研究科 教授 泉井 一浩
本講演では,情報学的アプローチを導入した新しいトポロジー最適化手法について解説します.具体的には,Karhunen-Loéve展開を用いた形状表現法とそのデータ次元削減効果を活用した差分進化法に基づく新たなトポロジー最適化手法,画像処理技術を応用した形状特徴の構築方法,そしてデータ駆動型のマルチスケールトポロジー最適化のトピックを取り上げます.これらの手法について,理論的背景と実例を交えながら、その効果と有用性を詳細に解説していきます.
休憩(15分)
3. 15:40-16:30(質疑16:30-16:40)
「異方性トポロジー最適化とその応用」
豊田中央研究所 野村 壮史
複合材料を用いた構造最適化を行う場合,材料の異方性を考慮に入れる必要があります.そして,その特性を最大限発揮するには,異方性材料の配向を考慮する必要があります.このような設計問題に対応した異方性トポロジー最適化と,その最適化結果を実際の構造物として成立させる方法について,いくつかのケーススタディを交えて解説します.
4. 総合討論 16:40-17:10
12月17日(火)
1. 13:10-14:00(質疑応答14:00-14:10)
「機械学習を用いたデータ駆動型の設計手法」
東京大学大学院工学系研究科 講師 米倉 一男
深層学習の進歩に伴って,機械学習を用いた設計手法が大きく様変わりしている.このようなデータ駆動型の手法は使用する機械学習モデルだけでなく,使用するデータセットによっても結果が異なる.本講演では機械学習を用いたサロゲートモデル,生成モデルを用いた逆問題の解法,深層強化学習を用いた最適化手法についてそれぞれ学習用データに触れつつ説明する.
休憩(15分)
2. 14:25-15:15(質疑応答15:15-15:25)
「生産技術における最適設計の活用」
金沢大学設計製造技術研究所 教授 北山 哲士
生産技術分野では,試行錯誤的な製造条件の決定がされている場合がほとんどである.本講演でははじめに,代表的なサロゲートモデルについて簡単に説明した後,機械学習を活用した最適設計法の概略を説明する.そして,薄板成形,鍛造,プラスチック射出成形を対象に,機械学習を活用した最適設計法を用いて製造条件を決定したいくつかの事例を紹介する.
休憩(15分)
3. 15:40-16:30(質疑16:30-16:40)
「トレードオフ分析をしましょう」
早稲田大学大学院情報生産システム研究科 教授 荒川 雅生
製品の開発・設計を有意義に行うためにはそれがどのようなものかを把握する必要があります.そのためには多目的最適設計を行うことをお勧めします.そして,トレードオフ分析です.トレードオフ分析をすることで自分が一体どんなものを作ろうとしているかを正確に理解することができます.トレードオフ分析を通じて,どの目的関数とどの目的関数が同じ動きをするか,相反するものなのかを明確にしていきましょう.
4. 総合討論 16:40-17:10
【定員】
50名
【参加費(税込)】
2日受講の場合:
正員・特別員(行事参加割引コード利用)・協賛団体一般30,000円,
正員(継続特典)・大学院生の会員(正員)・学生員・協賛団体学生15,000円,
会員外40,000円,一般学生15,000円.
1日受講の場合:
正員・特別員(行事参加割引コード利用)・協賛団体一般20,000円,
正員(継続特典)・大学院生の会員(正員)・学生員・協賛団体学生10,000円,
会員外30,000円,一般学生10,000円.
◆学生員から正員資格へ変更された方は,卒業後3年間,学生員価格にて講習会にご参加いただけます.お申し込みの際,「正員(継続特典)」を選択し,卒業年と卒業された学校名を「通信欄」にご記入ください.
◆大学院生の会員(正員)の方は「学生員」を選択し,「通信欄」に所属大学院名,課程・学年をご記入ください.
◆特別員(法人会員)で参加される場合,「行事参加料割引コード」のご利用で参加費は正員価格となります.お申し込みの際,「特別員」を選択し,「会員番号」に「行事参加料割引コード」(xxxxxxx-xxxx)をご記入下さい.
◆「特別員行事参加無料券」のご利用で,参加費は無料となります.「特別員(無料券利用)」としてお申込みの上,以下の担当職員まで「行事参加無料券(原本)」をご郵送ください.
〒162-0814 東京都新宿区新小川町4番1号 KDX飯田橋スクエア2階
一般社団法人日本機械学会 設計工学・システム部門担当 秋山宛
◆協賛団体会員の方は「協賛団体一般」「協賛団体学生」を選択し,「会員番号」に協賛団体会員番号,「通信欄」に協賛団体名をご記入ください.
【教材】
上記参加費には教材1部(DL版)代金を含みます.なお教材(DL版)のみご希望の方は,行事終了後,1部につき会員4,000円,会員外(協賛団体会員含む)6,000円(いずれも税込み価格)にて頒布いたします.ご希望される方は12/24以降に下記ページよりご購入下さい.
https://www.jsme.or.jp/publication/event-pub/
【申込締切】
12月9日(月)⇒12月11日(水)延長しました
【申込方法及び注意事項】
Payventより受付
URL: https://app.payvent.net/embedded_forms/show/66fc9a7a7083fe26be698ee8
■聴講料は,12月11日(水)までにご入金をお願いします.
■聴講料のお支払いには,クレジットカード(Apple pay,Google pay含む)・銀行振込のいずれかがお使いいただけます.
■銀行振込の際の振込手数料は各自でご負担いただきます.予めご了承ください.また,振込先の口座は申し込みごとに異なり,他の申し込みとまとめてのお支払いは出来かねます.
■銀行振込でのお支払期限は,原則としてお申し込みから3日以内です.ご入金が確認出来ない場合,こちらでキャンセル処理をさせていただきますのでご了承ください.
■お申込内容は,Payventより配信されるお申し込み完了メールからご確認いただけます.メールが届かない場合は「payvent.net」からのメールを許可するように受信設定をお願いします.
■原則として,決済後はキャンセルのお申し出がありましても返金できませんのでご注意願います.本ページからのお申し込みについては,集会事業申込規約にご同意いただいたものとみなします.
【領収書】
■領収書のお宛名には参加者の氏名が自動で記載されます.ご所属先を宛名に追加する場合は申込フォームの”領収書のお宛名”欄に記載をお願い致します.(こちらに氏名を入力しますと,宛名に氏名が重複しますのでご注意ください)
■領収書はPayventからのお支払い完了メールに記載されているURLよりダウンロードいただけます.
【問い合わせ先】
設計工学・システム部門担当 秋山 宗一郎/TEL:03-4335-7613/E-mail: akiyama@jsme.or.jp
柔軟媒体ハンドリング技術の理論と応用
【協賛(仮)】
精密工学会,日本時計学会,電子情報通信学会,日本トライボロジー学会,応用物理学会,計測自動制御学会,システム制御情報学会,情報ストレージ研究推進機構,電気学会,日本AEM学会,日本磁気学会,日本生体医工学会,日本表面真空学会,日本フルードパワーシステム学会,日本ロボット学会,エッジプラットフォームコンソーシアム,エネルギーハーベスティングコンソーシアム,日本非破壊検査協会、日本画像学会
【開催日】
・講義動画の配信(YouTube) :2024年11月21日(木) 9時 ~ 2024年12月19日(木) 17時
・オンライン講習日(Zoom) :2024年12月5日(木)
【講習会形式】
YouTube による講義動画の配信、及び、Zoomによるオンライン講習
本会書籍「柔軟媒体ハンドリング技術の理論と応用」を利用
【趣旨】
本講習会は,書籍『柔軟媒体ハンドリング技術の理論と応用』の著者本人及びその技術に精通した技術者によるオンライン講習会です.本書籍は,フィルムや用紙などの柔軟媒体を扱う上で,そのハンドリング技術の基礎や事例を1冊に纏めた技術書となっています.講習会には書籍代が含まれており申込者に送付します.
本講習会では,書籍の内容を解説した講義動画を事前に視聴していただき、オンライン講習日には受講者の皆様からの質問に回答します.
講習内容は,ウェブの搬送理論、柔軟媒体に作用する流体力理論、及び、これら理論を応用したウェブハンドリング設備の概論となっております.柔軟媒体ハンドリング技術の理論から応用まで学べる講義となっており,初めて柔軟媒体ハンドリング技術を勉強される機械技術者,研究者をはじめ,既に柔軟媒体ハンドリング技術を製品に導入して更に高性能化を必要とする方など,多くの方に役立つ内容となっています.
また,オンライン講習後も含めて約1か月間講義動画を視聴できますので,時間に縛られずに受講できます.是非ご参加ください.
【プログラム(暫定)】
■2024年12月5日(木)
15:00~15:30 ウェブの搬送理論 山田 健央(富士フイルム株式会社)
15:30~16:00 ウェブハンドリング設備の概論 山田 健央(富士フイルム株式会社)
16:10~16:40 柔軟媒体(ウェブ)に作用する流体力の基礎理論 渡辺 昌宏(青山学院大学 教授)
【教材】
本会書籍である「柔軟媒体ハンドリング技術の理論と応用」と配布資料(電子ファイル)を使用します.
http://gigaplus.makeshop.jp/jsmebooks/contents/5696_Pamphlet.pdf
配布資料は、ダウンロード方法を開催前に参加者にはお知らせし、書籍は郵送いたします.
講義動画配信日の2日前にYouTubeのリンクおよびオンライン講習ご参加Zoom(URL)をお知らせいたします。
【定員】
本講習会では定員を設けません.多くの皆様のご参加をお待ちしております.
【聴講料(いずれも税込・配布資料を含む)】※書籍代・郵送代込
正員・特別員(行事参加割引コード利用)・協賛団体会員 30,000円
学生員・大学院博士後期課程在籍の正員・正員(継続特典)・協賛団体学生員 20,000円
会員外45,000円
一般学生30,000円
【申込方法】
以下のURLより1名ずつお申込みください.
〈URL〉https://app.payvent.net/embedded_forms/show/66fb5262872aa32775899051
【申込締切】
2024年11月8日(金)
【聴講料の支払いについて】
■聴講料については,必ず11月8日(金)までに決済をお願いします.
■聴講料のお支払いには,クレジットカード(Apple pay、Google pay含む)・銀行振込のいずれかがお使いいただけます.
■銀行振込の際の振込手数料は,各自でご負担いただきます.予めご了承ください.また、振込先の口座は申し込みごとに異なり,他の申し込みとまとめてのお支払いは出来かねます.
■銀行振込でのお支払期限は,原則としてお申し込みから3日以内です.ご入金が確認出来ない場合,こちらでキャンセル処理をさせていただきますのでご了承ください.
■お申込内容は,Payventより配信されるお申し込み完了メールからご確認いただけます.メールが届かない場合は,「payvent.net」からのメールを許可するように受信設定をお願いします.
■原則として,お支払い完了後はキャンセルのお申し出があってもご返金できませんので何卒ご了承ください.
【領収書について】
■領収書のお宛名には参加者の氏名が自動で記載されます.ご所属先を宛名に追加する場合は申込フォームの”領収書のお宛名”欄に記載をお願い致します.(こちらに氏名を入力しますと、宛名に氏名が重複しますのでご注意ください)
■領収書はPayventからのお支払い完了メールに記載されているURLよりダウンロードいただけます.
※学生員から正員資格へ変更された方は,卒業後3年間,本会講習会への聴講は学生員価格にて参加が可能です.下記申込先フォームの会員資格は「正員(継続特典)」を選択し,卒業年と卒業された学校名を「通信欄」に記載ください.
※特別員の資格(正員扱い)で行事に参加される場合,聴講料は正員の価格となります.下記申込先フォームの会員資格は「特別員 行事参加料割引コード利用」を選択し,「会員番号」に「行事参加料割引コード」(xxxxxxx-xxxx)をご記入下さい.
※請求書の発行は,対応できかねますので,ご理解・ご協力の程,よろしくお願い申し上げます.
※申し込み後のキャンセルはできません.スケジュールをよく確認の上,参加申し込み頂きますよう,ご協力お願い申し上げます.
※「特別員行事参加無料券」を利用される場合,聴講料は無料となります.予め「特別員行事参加無料券(原本)」をご用意の上,「特別員」としてお申込みください.「行事参加無料券(原本)」を以下問合せ先にご郵送ください.
※協賛団体会員の方は「協賛団体一般」「協賛団体学生」を選択し,「通信欄」に協賛団体名をご記載ください.
【問合せ先】
〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番1号KDX飯田橋スクエア2階
一般社団法人 日本機械学会 IIP部門担当 北沢
TEL: 03-4335-7610
E-mail: kitazawa@jsme.or.jp
第35回 設計工学・システム部門講演会
企 画
設計工学・システム部門
協 賛(予定)
計測自動制御学会,システム制御情報学会,自動車技術会,情報処理学会,人工知能学会,精密工学会,電子情報通信学会,土木学会,日本応用数理学会,日本気象学会,日本計算工学会,日本建築学会,日本原子力学会,日本航空宇宙学会,日本シミュレーション学会,日本信頼性学会,日本設計工学会,日本船舶海洋工学会,日本知能情報ファジィ学会,日本バーチャルリアリティ学会,日本非破壊検査協会,日本ロボット学会,ヒューマンインタフェース学会,溶接学会,日本デザイン学会,ASME日本支部
開催日
2025年9月3日(水)~5日(金)
会場
明治大学 駿河台キャンパス(東京都千代田区)
趣旨
このたび,日本機械学会 第35回設計工学・システム部門講演会を,明治大学 駿河台キャンパスで開催する運びとなりました.
最適設計やシミュレーション工学,計算科学,AI・データサイエンス,設計方法論,デザイン科学,人間工学,感性工学,サービス工学,ヒューマンインタフェース,VR/AR,設計教育など,モノづくりやコトづくりに関連する設計工学を中心に,多岐にわたる学術分野を対象としています.技術者教育の一環である講習会の積極的な開催や,工学設計に関連する国内外の学協会との国際会議,特定の研究トピックに焦点を当てた他部門との合同シンポジウム等の継続的な開催など,異文化・異分野間の情報交換を積極的に行っており,また,産学連携が進んでいる点等も特徴的です.
社会課題解決に向けた次世代設計工学のビジョン創出と時代の変化に対応できる産学官連携を盛り上げていきたいと思いますので,多くのみなさまのご講演およびご参加をお待ちしております.
講演発表・D&Sコンテスト要項
設計やシステムに関わるさまざまな研究についての講演発表をオーガナイズドセッションおよび一般セッションにて広く募集いたします.
優秀な講演発表に対して「優秀講演表彰」,「日本機械学会(若手優秀講演)フェロー賞」を授与します.
(詳細は講演会HPをご参照願います)
問い合わせ先
〒162-0814 東京都新宿区新小川町4-1 KDX飯田橋スクエアビル2階/
日本機械学会 設計工学・システム部門 (担当職員 秋山 宗一郎)
TEL(03)4335-7613/FAX(03)4335-7619
E-mail:akiyama@jsme.or.jp
関連サイト
https://confit.atlas.jp/guide/event/dsdconf25/top(予定)
講演申込締切
2025年5月16日(金)
原稿提出締切日
2025年7月4日(金)
ロボットグランプリ ロボットスカベンジャー競技会
No.25-8 競技会「ロボットグランプリ ロボットスカベンジャー競技会」
企画 ロボティクス・メカトロニクス部門
開催日 2025年3月30日(日),10:00~17:00
会 場 東京都立産業技術高等専門学校 荒川キャンパス
(〒116-8523東京都荒川区南千住8-17-1)
趣 旨 ロボットスカベンジャー競技会は、ロボットグランプリで行われる競技種目の一つです。有線の遠隔操縦で動き回り作業ができる車両ロボットを2名のチームで作り,床に散らばるゴミ(ピンポン玉など)の回収能力を競います。 参加申し込みいただいたグループにはルールブック・製作ガイドなどの資料を送付いたします。 その指示に従ってロボットを製作ください。 指定するキットは有線遠隔操作盤を有する2台の模型車両です。 参加希望者には制作基本キットを郵送いたします。
会場アクセスURL https://www.metro-cit.ac.jp/information/access.html
参加費登録費 無料
定 員 なし
申込締切 2025年2月28日(金)
申込方法 Webエントリーシステムから参加登録をしていただきます。
詳細につきましてはロボットグランプリホームページ
https://www.jsme.or.jp/rmd/RobotGrandPrix/24th/index.html
を御覧ください.
問合せ先 ロボットグランプリ スカベンジャー競技実施担当
田中孝之(北大)、倉爪 亮(九大),河村 隆(信州大),
青木岳史(千葉工大),鈴木高宏(麗沢大),
堀 滋樹(都立産業技術高等専門学校)
E-mail:robotgrandprix.scavenger@gmail.com