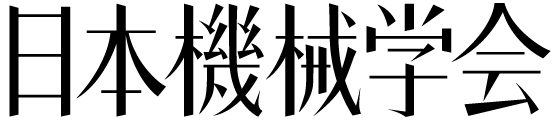2024年度定時社員総会特別企画 サステナビリティ・トランスフォーメーションに貢献する機械工学
日時 2025年4月24日(木)12:30-15:00
会場 明治記念館(東京都港区)およびオンライン(YouTubeによるライブ配信)
定員 対面:200名、オンライン:定員制限なし
※対面参加申込締切:2025年4月17日(木)正午
趣旨
今後30年間は、SDGsはもとより環境問題に対するカーボンニュートラルやグリーン・トランスフォーメーション、インフラの老朽化や防災・減災といったレジリエンス向上のためのデジタルツインの活用によるデジタルトランスフォーメンションなど、日本社会の一層の変革が求められています。機械工学は社会の基盤を支えるとともに社会を豊かにするための学問です。本特別企画では、「サステナビリティ・トランスフォーメーションに貢献する機械工学」をテーマに、機械工学が駆動するトランスフォーメンションに関わる取り組みを紹介し、日本の環境・技術・経済の変革を促進するための具体的なアプローチについて議論します。参加者がこれからの変革に対応するための知見を深める場とします。
申込方法 下記ウェブサイトからお申し込み下さい.
https://forms.office.com/r/vCu1CJhu62
プログラム
司会:大岩 孝彰(庶務理事)
挨拶:山本 誠(日本機械学会 会長)
講演① 12:35~13:00
「防災・減災と社会レジリエンス」藤田 聡(東京電機大学 工学部 機械工学科 教授)
工場、発電施設、配管、ポンプ、クレーン、建築設備等に代表される機械構造物は、1923年に発生した関東地震以降、多くの地震で被害を受けてきた。機械分野で対象とする構造物は多く、それぞれに要求性能も異なることから、耐震技術の一般化は困難なものになる。また、昨今、都市機能維持の観点から、重要施設への免震構造適用や地震時/地震後のエネルギーの安定供給や建物内の縦動線を確保する上で昇降機の重要性に注目が集まっている。本年は、兵庫県南部地震30周年ということもあり、社会レジリエンスを今一度見直す節目であると考える。
講演② 13:00~13:25
「エネルギーを取り巻く状況とカーボンニュートラルの実現」落合 誠((株)東芝 技術企画部 エネルギー領域技術責任者)
AI・デジタルの進展などでエネルギー需要は増加が予想され、これとカーボンニュートラルを同時に満足する必要がある。そのためには原子力や環境配慮型火力等の維持発展はもちろん、水力、地熱、太陽光、風力等の再生可能エネルギー、新型送変電や蓄電、省エネの分野でイノベーションの創出が求められる。また、エネルギープラントや機器の安定運用には、高度な運転、保守、検査、補修等の技術が重要である。本発表では東芝の事例を参照し、エネルギーを取り巻く状況とカーボンニュートラルの実現について概説する。
講演③ 13:25~13:50
「サーキュラーエコノミーが変革するものづくり」梅田 靖(東京大学 大学院 工学系研究科人工物工学研究センター 教授)
サステナビリティ・トランスフォーメーションは、人々の幸福の実現と広義の地球の資源消費のデカップリングを要求するものであるが、その構成要素の1つである「サーキュラー・エコノミー(CE)」は、より直接的に、ものづくりや価値提供手段の変革を求めている。本講演では、CEの基本的な考え方、CEが示唆する今後のものづくりの方向性、さらには、その実現手段としてのビジネスモデル変革と製品ライフサイクル設計の概要を紹介する。
講演④ 13:50~14:15
「プラスチック資源循環DXソリューション「RaaS」(Recycle as a Service)」 橘川 知彦(三菱電機(株) サステナビリティ事業推進部 リサイクル共創センター 技術営業統括)
三菱電機グループでは、使用済み家電から回収したプラスチックを再び自社の家電に用いる「自己循環リサイクル」を実施してきました。私たちは資源循環があたりまえな持続可能社会を実現するために、次の事業展開を検討しています。選別技術とデジタルを掛け合わせ、他業界へ適用できる形を模索し、選別装置やオペレーションノウハウを提供することで、顧客のプラスチックリサイクルを支援させていただく新規事業をご紹介します。
総合質疑 14:20~15:00
モデレータ 小木曽 望(大阪公立大学 大学院 工学研究科 航空宇宙工学分野 教授)