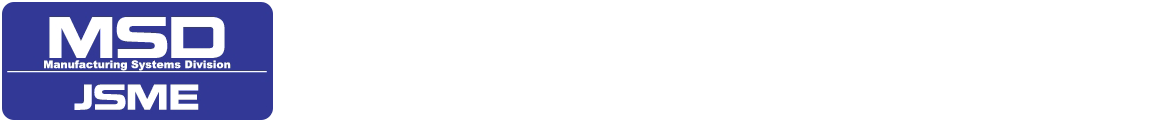96期部門長挨拶 -超スマート社会における価値共創型のモノづくりを目指して-

このたび,第96期生産システム部門の部門長を仰せつかりました神戸大学の貝原です. 微力ながら,本部門のさらなる発展に尽力させて頂きたいと思いますので,宜しくお願い申し上げます.
さて,我が国の2016年度から5年間における科学技術の総合的計画が示されている第5期科学技術基本計画の中で,新しい価値やサービスを持続的に創出するコンセプトとして,「超スマート社会 (Society 5.0)」が新たに提唱されました. この超スマート社会とは,「必要なもの・サービスを,必要な人に,必要な時に,必要なだけ提供し,社会の様々なニーズにきめ細やかに対応でき,あらゆる人が質の高いサービスを受けられ,年齢,性別,地域,言語といった様々な制約を乗り越え,活き活きと快適に暮らすことのできる社会」と定義されております.
さらにこの基本計画では,超スマート社会の概念に従い,先に科学技術イノベーション総合戦略2015で特定された,「新たなものづくりシステム」を含む先行11システムを統合する共通の基盤技術として,「超スマート社会サービスプラットフォーム」が示されています. ここで提唱されている超スマート社会およびその共通基盤的なサービスプラットフォームは,あくまで概念レベルの提唱であり,これからは,この具現化を可能とする科学的理論や方法論の確立が重要な課題であると言えます.
さてここで,総合戦略に謳われている超スマート社会とこれからのモノづくりの関係について少し考えてみたいと思います. 超スマート社会の定義において,モノづくりが果たす役割との関わり合いとして,ものやサービスを媒介とする社会のニーズへのきめ細やかな対応や質の高いサービスの提供などが挙げられます. そして,超スマート社会においては,従来の技術主導でモノ中心の価値提供(いわゆるGoods Dominant Logic)だけではなく,モノやサービスの作り手と使い手が超スマート社会を真に豊かなものとする価値を持続的に共創していくこと(Service Dominant Logic)が重要となります. さらに,そのような持続的価値共創の仕組みの提供が,超スマート社会サービスプラットフォームへの要件として強く求められると考えられます.
この実現のためには,単なる従来の自然科学系の取り組みだけでなく,新たな社会の仕組みを考えるための社会科学系学問領域との融合が必要不可欠となります. 一方で,我々の生産システム部門は,日本機械学会において,最も学際的あるいは横断的な学理を持つ部門であり,本学会において,超スマート社会の実現を考える上で重要な役割を担うことが期待されています. このことは,近年,モノづくりの世界において,色々と取り上げられることの多いドイツのIndustrie4.0や米国のIIC(Industrial Internet Consortium)など,IoT環境下での新たなモノづくりの形態において,CPS(Cyber Physical System)やDigital twinと呼ばれるシステム技術が大きな役割を果たしていることからも分かります. さらに,モノづくりにおけるIoTの範疇を,工場内や製品だけでなく,製品やサービスを利用するユーザまで積極的に含めることで,超スマート社会で謳われている社会のニーズへのきめ細やかな対応が可能になると考えられます. このような,価値共創型のモノづくりへの実現に向け,システム最適化やモデリング,システムシミュレーションといったシステム科学をコアに持つ生産システム部門は,強いアドバンテージを持っていると言うことができるでしょう.
このような状況に対応するため,現在,生産システム部門では,「つながるサイバー工場研究分科会CPPS: Cyber Physical Production System」と「AM(Additive Manufacturing)を軸とした生産システム革新研究分科会」という2つの研究分科会を擁し,精力的な活動を展開しています.これら研究分科会の成果は,生産システム部門講演会における報告にとどまらず,ここ数年は,毎年7月に東京ビッグサイトで開催される「生産システム見える化展」において,本部門が共催する形式の特別講演にて多数の参加者へアウトリーチを行い,高い評価を得ております.
また,次回の生産システム部門研究発表講演会は,2019年3月12日(火)に青山学院大学相模原キャンパスにて開催を予定しております.例年の講演会を踏襲し,注目のテーマに関する特別講演を企画するとともに,しっかりとした議論のできる研究発表の場にもしていく予定ですので,多数の研究発表・参加をお待ちしております.
講習会につきましては,生産システムシミュレーション技術と現場改善技術によるスマート生産時代の生産システム設計という内容で,座学形式にて実施を行う予定です.こちらへのご参加も宜しくお願いいたします.
1988年に,本部門の前身であるFA(Factory Automation)部門が設立され,途中2002年に生産システム部門として生まれ変わりながら,今年で30年の歳月が経とうとしています.このような経緯を見ても,本部門は,その歴史の中で,20世紀後半の自動化を核とする第三次産業革命から,現在のデジタル情報通信技術を核とする第四次産業革命へと時代の変化を先取りする形で活動を推進してきたと言えます.今後も,諸先輩方の努力により培われてきたこの伝統を受け継ぎ,モノづくりにおける新しい時代を,先導となって切り開いていきたいと思います.そして,生産システム部門が,産学官を問わず,同好の士が一堂に会し,ますます活気のある場となるよう努めて参りたいと思います.引き続き,皆様のご支援とご協力を宜しくお願いいたします.
2018年度(96期)部門長 貝原 俊也(神戸大学)