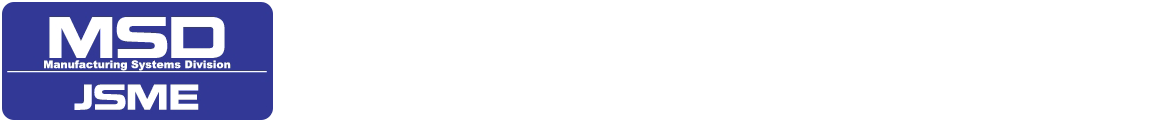92期部門長挨拶
いつの間にか、“製造”あるいは“製造業”ということばよりも、“ものづくり”というよりソフトなキーワードを多くの人が好んで使うようになりました。3Dプリンターへの期待の高まりが示すように、生産プロセスの概念や、そこで働く人々の価値観、そして製造業への期待も大きく変わろうとしています。そうした時代の大きな変化のど真ん中に位置しているのが“生産システム”という看板を掲げた我々生産システム部門です。急流や濁流に流されず、逆に自ら流れを作り出していくためにも、生産システム部門の立ち位置を、この場を借りて会員の皆様と共有できたらと思います。
あらためて定義するまでもありませんが、システムとは“複数の要素で構成され、個々の要素が複雑に関係しあうことで、全体としてまとまりのある振る舞いをするしくみ”です。ただし、世の中のさまざまなシステムは、以下の図のように、人工物システム、経営システム、そして社会システムの3種類に分けて議論する必要があります。なぜなら、それぞれの種類ごとに、その研究アプローチが大きくことなるからです。まず、多くの工学系の研究は、その対象が人工物システムであり、自然法則に支配される世界となります。もちろん、ユーザという形で人が関与しますが、それは設計対象の外側にいます。
一方、社会科学系の研究対象は社会システムとなります。その構成要素には直接モノや個人は登場しません。そして、それらの2種類のシステムの間に位置づけられる経営システムは、複数のモノと複数の人や組織が織りなす現実の企業活動そのものです。そこでは、人の複雑な意思決定がからみ、結果の再現性が保証しにくい分野です。

生産システム部門が対象とするのは、この3種類のシステムのどれでしょうか? 生産システムは、人工物システムであると同時に経営システムという側面を強く持っています。つまり、生産システム部門は、これらの異なる種類のシステム研究の間隔を埋める役割を担っているのだと思っています。経営システムの研究でありながら人工物システムを強く意識した研究、あるいは人工物システムの研究でありながら、同時に経営システムの課題解決にも取り組んでいる研究など、そうした学際的あるいは横断的なところが生産システム部門の研究の大きな特徴であり、アドバンテージではないかと思います。
こうして俯瞰的な視点から研究対象領域をとらえると、人工物をそのメインターゲットとする日本機械学会の中にあって、生産システム部門は、学会全体の中心部分からは最も遠いところにその軸足を置いており、悪く言えば辺境、よく言えばその学問領域をさらに拡大することが可能なフロンディアにその陣営を構えています。そして、時代はまさにこの学問領域のさらなる充実と発展を望んでいるのです。
現在進行中の情報革命の中で、インターネットが人と人、そしてモノとモノとをつなぎ、製造業はますますサービスやネットワークの比重を高めたものづくりにシフトしています。国内で作っても海外で作っても“ものづくり”の本質はかわりません。また、工場の内側で作っても、工場の外側にある消費者により近い場所、あるいはサービスの現場で作っても、それは“ものづくり”です。我々は、変化しつつあるこうした様々なしくみを“生産システム”として、工学的な立場からエンジニアリングしていかなければなりません。
アベノミクスの第3の矢がいよいよ動き始め、総合科学技術会議が中心となったイノベーション政策がスタートしました。イノベーションの起点となる取り組みをいかに発信していけるかが問われています。工場がスマートファクトリーとなり、ITとのさらなる融合が進み、製造業のサービス化、グローバル化とボーダレス化、ネットワーク化とオープン化の流れの中で、付加型製造など新プロセスの活用、エコ技術の取り込み、レジリエンス、セキュリティー、知財やビジネスモデルの検討など、生産システムに関する研究領域が急速に拡大しています。
要素技術の研究から、システム技術の研究へ軸足を移すと、さまざまな異質な要素の関係性の中から、新しい価値が生れてくる面白さに気が付きます。同様に、メンバーひとりひとりの研究が、部門の活動のなかで相互に結び付くことで、新しい価値が生れる可能性を多くもっています。そうしたコラボレーションの先に、新しい時代を創るイノベーションの芽を見つけることができるかもしれません。
我々の前身であるFA(ファクトリー・オートメーション)部門が“生産システム部門”に名称を変えてから今年で12年になります。FA部門の設立時までさかのぼれば、すでに四半世紀が過ぎました。これまでの素晴らしい部門の伝統を受け継ぎ、さらに時代のニーズに対応し、あるいは先取りする形で、生産システム部門をますます活気ある組織として、より多くの皆様の研究の場、情報収集や発信の場、そして交流と通じたコラボレーションの場となるよう努めたいとおもいます。どうぞよろしくお願いいたします。
2014年度(92期)部門長 西岡靖之(法政大学デザイン工学部)