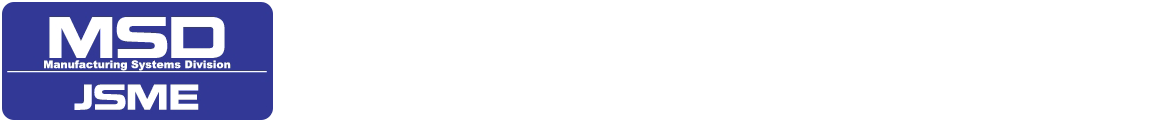90期部門長挨拶 生産システムの発展のために
このたび第90期部門長を務めさせていただくことになりました中央大学の平岡です.責任に身が引き締まる思いですが,部門の皆様の活動を支えていけるよう微力ながらがんばっていきたいと思っています.どうぞよろしくお願いします.
生産システム部門の対象は,ものづくりに関するシステム全般であるため,たいへん広い範囲をカバーします(今年度新たに作成したポリシーステートメントでは「極端な例をあげれば,ネジ1本の規格の策定に始まり,国境を越えたサプライチェーンの構築まで」と書きました).機械工学の分野には材料力学,熱工学,流体工学などの基礎的な分野とエンジン,ロボットなどの応用的な分野がありますが,生産システムの分野では,そうした基礎と応用を組み合わせて生産システムとして横断的に統合する視点が加わります.さらに特徴的なことは,その守備範囲が常に変化していくことです.生産システムは企業活動の中心にあり,経済活動,社会情勢などと切り離せない関係があるため,そうした経済,社会などが原因の,言わば外から生じる「外圧」に対して直接対応しなければならない立場にあります.リーマンショックやヨーロッパの金融危機,日本の労働者人口の減少とアジア新興国の勃興,東日本大震災やタイの洪水,など次々押し寄せる問題に対して,生産システムの技術者,研究者は第一線に立って解決策を考えていかなければなりません. このため,古くはFMS,CAD/CAM,最適化に始まって,ICT化,サプライチェーン,環境対応,ライフサイクル,プロダクトモデル,自律分散,見える化,等々,多くの新しい概念,視点,手法が提案され開発されてきました.最近では,グローバル化やレジリエンス(災害によるダメージから素早く復旧する能力)などが議論の中心になっています.注意しなくてはならないのは,単なる言葉遊び,バズワードに陥らないよう,紛れのない定義を定め,それに基づいて議論をすることです.また,ある状況で有効な手法が,違う視点からは問題になる場合もあります.平常時には最適な手法が,災害時には被害を増大する原因となるかもしれません.このように考えてくると,月並みかもしれませんが,既存の技術的手法の体系をきちんと整理し,各手法の適用範囲と位置づけを明確にすることがたいせつだと思います.変化の激しい分野であるからこそ,このような努力が必要だと考えています.遠回りかもしれませんが,このような地道な活動により,今直面する問題の適切な理解が促されるとともに,解決のための道筋を見つけやすくなるのではないでしょうか.会員の皆様にぜひいろいろご教授,ご協力を賜りながら考えていきたいと思います.
生産システム部門では,春の部門講演会,秋の大会に加えて講習会,見学会を通じて,生産システムに関する議論の場を提供していきます.3月に武蔵大学で実施した部門講演会では,企業の方にその状況やかかえる問題を報告していただき議論するセッションを設けて,講演者,出席者の双方から好評をいただきました.日野自動車の見学会にも多くの参加者がありました.今後とも引き続きこのような試みを実施していきたいと考えています.生産システム部門は小さな部門ですが,皆様のご協力を仰ぎながら,日本のものづくりを支える質の高い議論の場を作っていければと考えています.どうぞよろしくお願い致します.
2012年度(90期)生産システム部門長 平岡弘之(中央大学)