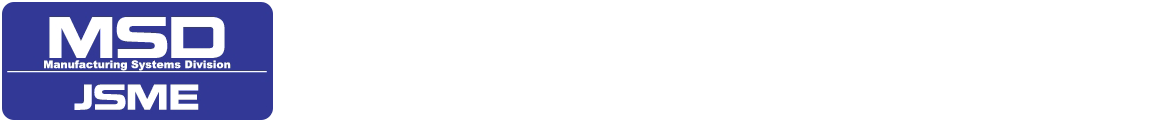89期部門長挨拶 「グローバル生産のための生産システムへの期待」
2011年度,日本の製造業は混乱の中からのスタートとなった.その理由は,言うまでもなく,2011年3月11日に発生した未曾有の地震である.それは,想定外の大きさの津波を誘発し,原子力発電所の事故を引き起こした.様々な報道では,“未曾有”,“想定外”といった言葉が多用され,予想を超えた事実を説明した.未曾有の地震は,原子力発電所の事故のみならず,想定外の被害をあらゆるところに与え,岩手県,宮城県,福島県,茨城県の製造拠点の活動がストップせざるをえない状況になった.ジャストインタイム生産方式において,物流(サプライチェーン)が途絶えることになり,世界中の製造拠点の製造計画に影響を及ぼした.日本の地方の一つの工場が生み出す製品の製造がストップしたことによる影響の大きさに驚かされたのは,私一人ではなかったのではないだろうか.生産システム技術者として,この状況は想定外だったのだろうか.想定はしていたとしても,現実の状況の中では,製造技術の観点あるいはコストの観点から他の製造拠点を並行して選択できなかったことも考えられる.いずれにしても,機械学会生産システム部門に嫁せられた役割として,今回の物流の混乱を勉強(分析)し,総合的な視点でどのような物流システムが現実の仕組みとして妥当なのか精査することが求められている.
日本の製造業の空洞化現象が始まって久しい.言い換えるならば,グローバル生産体制になってきている.グローバル生産体制に移行する理由は,安い労働力・低い税率・安価なインフラ設備などを求め要求に見合った拠点(場所)で生産するため,できるだけ消費地に近い場所で生産し市場へのスムーズな製品供給を狙うため,世界中への製品提供のために生産拠点を分散するためなど,いくつか考えられる.いずれの場合も,海外に生産拠点を置くことになる.このとき,海外の生産拠点の生産技術を向上しなければならない.すなわち,技術移転(技術流出?)が当然のこととなる.技術移転(技術流出?)は,望むことではないだろうが,避けることができないという立場に立つならば,資源・土地を持たない日本にとって,今後何十年間も,そして永遠に日本から世界に革新的な製造技術・システムを提供し,最先端モノ作りの先駆者と続けることが,日本が世界に果たすべき貢献や世界における位置づけを保ち,また,現状の生活を維持するために必須の課題である.
グローバル生産体制では,グローバルな部品調達を含めた生産システムが必要であることは言うまでもない.海外において,サプライチェーンを含め,生産システムが実効的に稼働しているのであろうか.現状では,生産設備のメンテナンスや簡単な部品の調達のために,生産拠点周辺(現地周辺)の生産技術を向上することに力点が置かれているのではないだろうか.可能な部品は周辺から調達しているが,周辺地域の生産技術の更なる向上に期待している感もあるようである.いずれにしても,現在は,東南アジア諸国,BRICsあるいは今後生産拠点となり得る国々の生産技術を確立している段階で,その後に生産システムの実効導入が始まると考えられる.企業全体あるいは工場全体の生産システムは,ひとたび導入されれば,工作機械を取り替えるように,あるいは個々の加工技術を変更するように,簡単に置き換えすることは容易ではない.ある意味で,生産システムは,その企業あるいはその工場の肝を仕切ることになる.このような観点で,生産システム技術が,今後,グローバル生産体制における日本モノづくりの展開(世界戦略)の基礎となると考えられる.前述のとおり,最先端加工技術を開発し世界に提供し続けることは重要であるが,それに加えて生産システムのグローバル展開を計画的に遂行することが,今後の日本のモノづくり力を発展させるためにキーとなると思われる.そのために課せられた生産システム部門の責任の重さを感じ,生産システム部門として,グローバル生産システムの構築・展開に関して積極的に議論の場を作っていきたい.
2011年度(89期)生産システム部門長 青山英樹(慶應義塾大学)