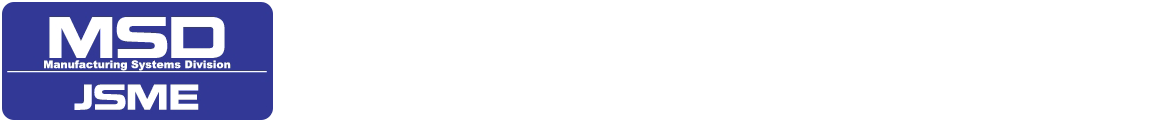86期部門長挨拶 「生産システム部門の「見える化」を目指して」
このたび第86期部門長を努めさせて頂くことになりました.皆様のご支援ご協力を得ながら任期中少しでも部門の発展に貢献できるよう努力したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます.
最近、「(産業および技術分野としての)生産システムの現在の課題って一体なんでしょうね?」と周囲の方々数人に聞いてみたことがあります.回答は省略しますが、それぞれご経験のある方々にとっても「改めて聞かれるとなかなか難しい問いですね」というような反応でした.これは私自身に発した問いでもあり、改めて、当部門、ものづくりの技術、我が国製造業などの現在と将来について考えざるを得ませんでした.
機械学会に限らず一昨今は学会のアクティビティ低下への危機感が叫ばれています.とりわけ機械学会の中でも小さい当部門におりますと、これを痛切に感じるところです.学会会員はそれぞれ専門部門へ登録するわけですが、当部門の場合は第一登録の人数よりも第二登録メンバのほうがかなり多いというのが実態です.これは生産システムそのものが学際的そして総合的な分野であることの証拠でもあり、いちがいに問題視することではありません.しかし部門の活性化を考える上で、生産システムの再定義と今後のアクションを考えてみるためには一つの指標であると思えます.
私自身は当初情報機器分野、ついでロボットメカトロ分野で機械学会のお世話になり、さらにネットを活用したものづくり支援というキーワードで生産分野に関ることになり、今日に至っています.ものづくり分野ではICT化、ネット化の導入で日本のものづくりを変革するという気概で仲間といろいろやってきました.しかしグローバルな視点で日本のものづくりを考えた場合、「ICTの導入で」、という単純な構図だけで種々の課題が解決するわけではなく、基盤技術から経営戦略まで幅広い知恵の結集が不可欠であることは皆様ご推察の通りです.したがって生産システム技術の研究開発においても、アカデミズムの世界と産業界とが本音を出しての問題発掘、課題解決がますます重要になると思います.
以上のような話は話として、具体的には生産システム部門を活性化していくことが私自身に課せられた主要課題です.このため部門の委員会も、学術活性を志向した技術企画委員会、部門事業を飛躍させる事業企画委員会と名称を一部変更しました.ネット時代にはその効能を生かした広報宣伝強化も不可欠です.また学際的な部門の強みを生かして、他の部門や団体との連携事業、さらにはユニークな大学や企業そして個人にも着目し、部門への持続的な刺激と各種の事業アイデアにつなげていければと思っております.これらのアクションにより、生産システム部門を拡大発展させ、会員の皆様へ貢献するとともに部門の事業収益基盤も磐石にする、そうした部門への元年にすべく、皆様と一緒にがんばっていきたいと思います.ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
2008年度(86期)生産システム部門長 柿崎隆夫(NTTアイティ)