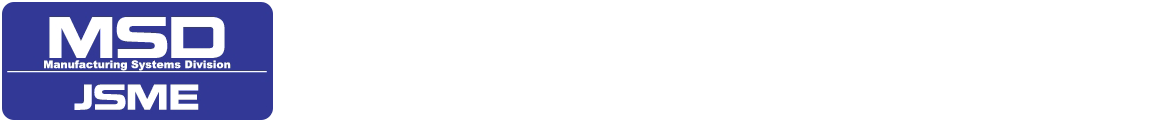84期部門長挨拶 「ものづくりが変化する中での生産システム部門の役割」
生産システム部門が関わる範囲はかなり広く捉える必要があると思います。図に示すようなサプライチェーン、エンジニアリングチェーン、及び全体を通してのライフサイクルマネジメントが包括的に含まれると考えています。また、図には明示的には表されていないものの、全体を通したエンジニアリング情報の流れ、販売量や生産進捗などマネジメント情報の流れ、ものの流れを支えるロジスティクスなども生産システムを構成する重要な要素だと考えています。

企業の目で見ても生産システムは、この20~30年で大きく変遷してきています。本部門の前身がFA部門であったように、自動化というのは重要なテーマでした。数多くの自動化機械、ラインが生み出され、省力化、品質の安定などに大きな成果を上げてきました。もちろん今でもこの領域が重要であることは言うまでもありませんが、要求されるものが変化してきていると感じています。即ち、生産の形態が大量生産から多品種少量、変種変量生産へと変化してきたように、変化・変動にいかに効率良く対応できるか、という点が重要になってきています。変化・変動の基は技術であったり、お客さまのニーズであったり、部品材料の進化であったり、様々な要因が考えられます。これを克服するために、情報の流れをスムーズにする、生産領域に閉じて考えずに開発・資材調達・販売・サービス領域まで拡大して全体を最適化する、いわゆるサプライチェーンマネジメントといった考え方もひろまってきました。更には保守から廃棄まで含めたライフサイクルマネジメントへと拡大しています。シーズ側即ち研究開発から見れば、さまざまな仕事がバーチャルな世界へと移行してきています。最初は開発設計、エンジニアリング領域のバーチャル化が進んだと思います。様々な解析や設計評価がコンピュータ上でシミュレーションできるようになり、開発リードタイムの短縮や試作回数の削減などにつながっています。最近では生産準備領域でのバーチャル化へと進み、例えばロボットの作業のオフラインティーチング、人の作業まで含んだ工程設計への適用などの事例も出てきました。また、地球シミュレータのように従来は手の出なかった長期の気候シミュレーションがコンピュータ上で実現できるまでになってきています。今後は錯綜する大量のデータの中から変化を読み取るためのデータマイニング技術なども、生産システムに適用できるかもしれません。
もう一つ重要なのは、製品そのものも大きな変革の波を受けていることです。機械加工技術の高度化により、超小型機器やバイオチップなど、従来では考えられない製品が生まれてきています。こうした進化がいろいろな所に現れてきていることは、デジタルカメラが主流になってきているカメラを例に取るまでもないでしょう。また、家電製品や携帯電話などはファームウエアなどと呼ばれる組込みソフトの割合が非常に高くなり、従来の大型基幹システム並みの機能が組み込まれています。当然こうした変化はものづくりのための生産システムに大きなインパクトを与えます。
このような様々な変化の中で、いかに効率よく変化・変動に対応していけるかを技術、システム、方法論、理論などの側面から探るのが生産システム部門の役割ではないかと考えています。
2006年度(84期)生産システム部門長 五十嵐 賢一 (日本電気株式会社)