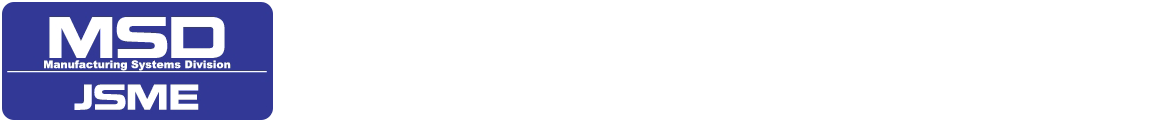【委員会報告】部門活性化に向けた検討報告(2024.9)
-
はじめに
第101期生産システム部門事業企画第三委員会では、部門活動を活性化するための施策を検討することを目的として活動を行った。具体的には、生産システム部門の部門活動について広くご意見を頂くために、2023年および2024年の生産システム部門研究発表講演会参加登録者の皆様を対象としてアンケートを実施した。本報告書では、上記アンケート集計結果、および、第101期 第4回(臨時)運営委員会にて運営委員の皆様より頂いた活性化に関するご意見と、そこから浮かび上がった検討すべき施策等について、事業企画第三委員会で議論した結果をまとめる。
-
活性化施策提案
○会員間の双方向コミュニケーションの場の開催
アンケートにおいて参加者が部門講演会に期待することとして多数を占めた項目として、普段交流が少ない会員間(企業関係者⇔大学関係者)の交流が挙げられる。また、学生と企業がつながる仕組みを構築し、多くの理系学生が興味を持っている企業の研究について知る機会を設けると良い、であるとか、企業側としても学生に自社をアピールし、間口を広げる場があると良いなどの意見も寄せられている。
それらに応える形で、大学と企業の交流を促進する場を企画・設定する。具体的には、各企業の紹介を行い、生産システムが関わる仕事、研究等について説明いただくコーナーを設ける。現在も企業展示は行われているが、インターン学生や就職志望学生の獲得、大学関係者との交流を主眼とした企画とすることで、これまで展示を行っていない企業にも訴求することが可能であると考えられる。また、就職を希望する学生、企業研究所でのポストを探しているポスドクの方、大学の先生方が疑問に思っていることなどを気軽に企業の方に質問して頂けるようにすると良い。
このような場を通じて生産システムに関わる企業に就職する学生が増加すれば就職後も引き続き生産システム部門に関わっていただけることが期待でき、結果的に若手会員の維持、獲得につながる可能性もある。開催の場としては部門講演会に合わせて実施するのが良いと思われる。
なお、集客やコミュニケーション促進の面では企業関係者⇔大学関係者間の交流に限定せず、企業間、大学間の交流も含めた会とする、気軽に参加可能なオンライン形式とする、ポスターセッションの一部の時間を軽食付きの懇親会を兼ねた場とするといった方法も考えられる。○若手の参加促進
アンケートにおいて20代、30代の若手の部門講演会への参加数は全体の4分の1程度にとどまっており、課題の1つとなっている。また、運営委員会においても若手の参加促進を求める意見が複数見られた。
見学会において参加費を必要最低限の額とした結果、参加者からは参加しやすくなったとの意見が寄せられたことから、部門講演会等においても若手を対象とした参加費の割引を行うことが参加促進の一助となると考えられる。また、座長に指名されることで部門講演会に参加しやすくなる(特に現地参加の必要性を会社に説明しやすくなる)とのご意見もあり、若手の方への積極的な座長依頼が有効であると考えられる。さらに、座長を引き受けて頂いた若手の方は懇親会にご招待する、もしくは懇親会費を割り引くなどにより、若手の方との交流促進にもつながることが期待できる。○コーヒーブレイクの開催
アンケートにて参加者の期待が大きかった会員間の交流を促進するための一つの施策として、部門講演会でのコーヒーブレイクの開催も有効であると考えられる。セッション間の休憩時間を長めにとってコーヒー等のドリンクを提供し、参加者間で議論、会話する機会を設けている学会も多く(例:統計関連学会連合大会)、かつ、それらの会場は押しなべて盛況であることが多い。小粒な施策ではあるが、その反面実施が比較的容易であり、活性化の一助となると考えられる。ただし、休憩時間の延長が必要であることからこれまでの部門講演会とは異なるスケジュールとなり、部門講演会の企画・運営を行う方の負担増につながり得る点には留意を要する。また、部門講演会はIIPとのコロケーション開催であるため、IIPとの調整、合意が必要となる。活性化施策案の一つとして前記した双方向コミュニケーションの場をコーヒーブレイク会場とするのも一案である。○オンデマンド視聴の導入
運営委員会でのヒアリングにおいても要望が複数挙げられた項目である。例えば人工知能学会では、発表日の2日後の朝にはほぼすべてのセッションがオンデマンド視聴できるようになっており、かつ約1か月間にわたって制限なく視聴が可能である。別のセッションを聴講していた、業務の都合で聴講できなかったなどの場合でも後日あらためて聴講が出来ることは参加者にとって利便性が高く、満足度向上に効果が高いと思われる。また、企業参加者は時期的に部門講演会参加が難しい(年度末開催のため)という意見が寄せられているが、その点を解決する一助にもなり得る。一方、現地参加者の減少を招くおそれもある点には留意を要する。○分科会の設立、勉強会、講演会の開催
AI、協創ロボットなど、困りごとに直結する分科会設立を求める声も運営委員会でのヒアリングにおいて寄せられている。部門講演会にて実施された最新トピックス(生成AI)の特別講演の評判が良く、生成AIに代表される新技術の情報収集がイベント参加の動機となるという声も寄せられていることからも、生産システム×AI、生産システム×IoT、生産システム×最適化、生産システム×デジタル化などを題材とした分科会設立、もしくは勉強会の開催は活性化に向けての良い施策になり得る。
なお、勉強会、講演会の開催に関しては、様々な専門性を有する会員が数多く所属している機械学会の一部門であるという利点を生かした、機械学会ならではのイベントに出来ると良いという意見もいただいている。例えば他部門との共催とすることにより、異なる分野、所属の方との相互交流の機会ともなりうると考えられる。この場合、共催とする他部門としては、シナジーが期待できる部門としてアンケートで名前の挙がった設計工学・システム部門、生産加工・工作機械部門、ロボティクス・メカトロニクス部門、情報・知能・精密機器部門等の中から開催テーマに応じて検討を行うのが良いと思われる。
さらに、学生を含む若手には今後の日本のモノづくりがどうなるかを気にしている方も多いと思われる。若手会員獲得の観点から、それらを題材としたシンポジウムのような形で産官学が議論する場、イベントを設けるのも一案である。