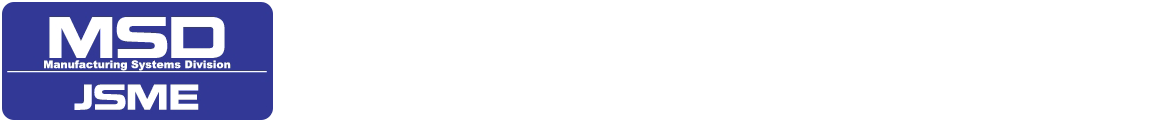98期部門長挨拶

第98期生産システム部門の部門長を務めさせていただきます東京大学の梅田です。どうぞよろしくお願いいたします。
生産システム部門は、産学が連携して、むしろ、産が主導して、システムの視点から、ものづくりに関するあらゆる問題を研究し、解決策を導出し、実践する活動を、また、研究や問題解決を通じた研究者・エンジニアのネットワーキングを支援、活性化することを目標に、参加する皆さんの刺激になる、魅力のある部門でありたいと考えています。このとき互いに関係する2つの視点が重要だと考えています。1つは、産業界の皆様の生産システムで今起きている足下の問題をきちんと把握し、その解決に貢献することです。他の分野と異なるこの分野の特徴として、学の人間は、生産システムを持ってもいないし、本質的な意味でよく分かっていないという点が挙げられます。その意味で、産学連携をベースとして、「今」の問題を把握し、解決することが重要だと考えます。
もう1つは、生産システムの「明日」の姿を明らかにすることです。生産システムは、価値を産み出し、提供するシステムであり、生産対象で言えば、ハードウェアのみならず、サービスやプラットフォームとの連携も今や必須のものとなりつつあります。対象とすべき活動範囲で言えば、エンジニアリングチェーン、サプライチェーンの全範囲に関連します。また、近年のサーキューラー・エコノミーなどの流れで言えば、製造販売後の使用、保全、再生・再利用を含む循環などの製品ライフサイクルも当然対象範囲となってきます。このような対象範囲の拡大の中で、解決すべき課題、武器となるEnabling Technologyも変化しています。後者についていえば、IoT、AI、Cyber Physical Systemなどのデジタル革命を構成する技術がまさに生産システムにおいて使いこなしの時期に入ってきました。ここで後れを取ると巻き返しが難しくなってくる危険性があります。解決すべき課題について言えば、サステナビリティ、レジリエンスに加えて、資源循環こそが産業競争力になるという欧州のサーキューラー・エコノミーに関する一連の動き、そして何より、今現在起きているコロナ禍の中で、withコロナのものづくりがどのような姿形になって行くのか、行くべきなのか。まさに、これまでとは次元の異なる柔軟性、即応能力、企業経営・企業戦略との接続性が、上述の広義の生産システム全体に求められているのだと考えます。この意味で生産システム研究は未発掘の鉱脈の宝庫です。これまで、生産システムの分野で活用されてきた技術、工学的方法論だけではなく、異なる分野のものの見方、技術、方法論を活用して、新しい研究テーマや方法論が今後数多く生まれると確信しています。そのプロセスを通じて、生産システムの「明日」の姿が見えてくると思うのです。
生産システム部門はこれまで、多くの製造メーカが参加するIVI (Industrial Value Chain Initiative)の設立に発展した「つながる工場」の提唱と実現技術の開発(現在は、「つながるサイバー工場MFG2040研究分科会」として活発に活動中です)、早期からの「Additive Manufacturing」への取り組みなど、様々な新しい活動を行ってきました。このような時期ですので、むしろこのような危機的な状況を糧として、新しいものづくりの姿を考えるきっかけを皆さんに提供できるよう励みたいと考えております。
日本機械学会において今年度から新部門制の試行が始まり、部門間連携の推奨が始まります。今年度の部門運営は、折角ですので様々な連携を試行し、異なるものの見方との出会いを企画して行きたいと考えています。日常的にはまだまだwithコロナ状態で、オンライン活動が中心となり、皆様にはご不便をおかけすることと思います。しかしながら、皆さまにとって魅力がある、参加したくなる部門となるよう、微力ですが部門運営に尽力したいと考えております。皆さまからのご意見、ご提案がカイゼンにつながりますので、お気づきの点などありましたらお気軽にお声がけください。ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
2020年度(98期)部門長 梅田 靖(東京大学)