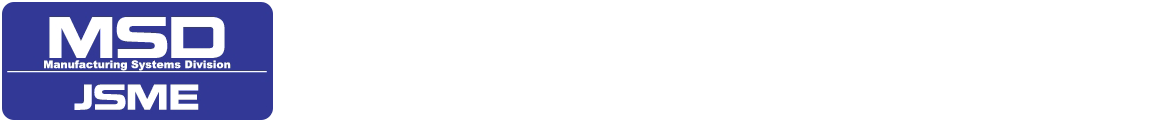91期部門長挨拶 生産システム部門の活動について
近年の生産システムに関する国際的な動向として,米国では,2011年6月に先端製造パートナーシップをスタートさせた.これにより5億ドル以上を投資し,米国の大企業とトップレベルの大学が連合して取り組んでいる.また,英国では,政府は通称カタパルトとよぶ技術イノベーションセンターの設立をすすめており,その一環としてMTC(Manufacturing Technology Centre)を設立した.これは,大学と産業界のギャップを埋める役目ももつ.また,独国ではフラウンホーファー研究開発機構を中核とした製造にかかわる科学技術システムが従来から機能している.以上のように,生産システムに関しては,国際的に厳しい研究競争および技術開発競争となっている.
このような生産システムに関する国際的な動向の下,本部門が行うべき活動について考えてみる.生産システム工学は,ものづくりの基礎学問として重要であるが,長年の研究開発にもかかわらず,学問として十分に体系化されているとは言えない.機械学会は,「機械工学便覧デザイン編β7生産システム工学」を出版し,図1中左側に示す目次(抜粋)の様に学問の体系化を行っているが,生産システム部門に関係する研究者に十分に浸透していない.そのため,生産システムの学問の体系化を促進する活動(例えば,便覧の改訂とその広報の継続的な活動)が重要である.
一方,生産システム関連の研究の目指すべき方向を示すことも,本部門の重要な活動の一つである.例えば,近年注目を集めている人や環境に配慮した生産システムは,社会的価値と経済的価値を生み出す効果が大きい.そのため,国内産業全体の底上げを目指す,生産システム全体の視点からの研究開発が望まれている.
このような期待が寄せられる中,生産システム部門に関係する研究者は,時代背景も踏まえ取り組む研究領域を模索してきた.近年における機械学会和文・英文論文集に注目すると,図1右上側に示すような研究課題が挙げられる.
以上を踏まえると,生産システム関連の研究の目指すべき方向として,図1右下側に示すような課題が考えられる.すなわち,継続的に取り組むべき課題として,これまで生産システム部門に関係する研究者が得意としてきた標準化,産業応用(部門講演会において別刷りが不要なセッションを設けている)に関する継続的な取り組みが必要である.
また,新たに取り組むべき課題として,国際的な動向に対応するためアディティブ・マニュファクチャリング,グローバルサプライチェーン,国内の社会的・経済的価値を生み出す効果が大きい人/環境に配慮した生産システム,生産システム部門に関係する研究者が独自に取り組み始めているサービス,レジリエンスなどの課題が挙げられる.これらの課題は,取り扱うべき対象または範囲が異なるが,そのモデル化や最適化のプロセスで共通の方法を用いる場合が考えられる.そのため,これら課題について,認識と議論を支援するための活動(講習会,講演会など)が重要であると考える.

2013年度(91期)生産システム部門長
塩谷 景一(三菱電機(株))