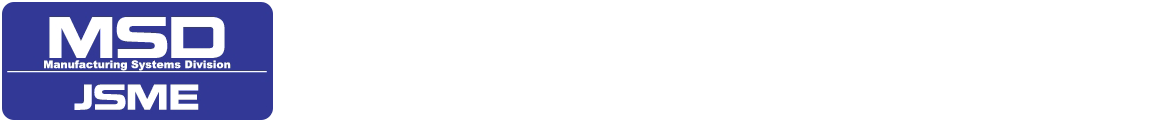85期部門長挨拶 「今後の「ものづくり」における生産システム部門の役割」
ものづくり」企業においては,自然環境および社会環境への負荷を考慮したうえで,多様なニーズに対応する高品質で多品種の製品を,適切な時期に,適切なコストで,適切な量だけ生産することが求められている.そのため,生産システムの範疇で考慮すべき問題は,多岐にわたり拡大しつつある.今後の生産システムにおいて検討すべき課題をまとめると図1のようになる.

図1 生産システムにおける検討課題例
図中の中央線は,製品の企画・設計・開発,生産システムの開発・運用・統制,および生産システムの構成要素の開発・運用・制御に関する問題を表している.このうち,製品の企画・設計・開発では,顧客の多様なニーズに適合するとともに,他の製品と差別化することができる高品質・高機能の製品を短期間で開発することが求められる.
生産システムあるいは生産プロセスでは,自然環境および社会環境との調和を考慮した生産システム技術,生産システム内における作業者などの人と共存することができる計画・運用・統制技術が求められる.特に,人の持つ高度な技能・技術を有効に生かすとともに,人の向上心あるいはモチベーションを高めるシステムがもとめられる.人間中心のシステムとしては,セル生産システムが広く適用されているが,今後は,人間が行うセル生産プロセスと自動化された生産プロセスとの協調が重要になってくる.
生産システムの構成要素,すなわち生産設備については,生産性,精度および品質はこれまで以上に求められるのは当然として,作業を行う人に対する親和性および協調性が求められる.
図1の横軸に対応するグローバル生産と地域密着型生産とは,相反するように思えるが,これらは生産対象製品,生産プロセスおよび社会環境などの観点から適切に使い分ける必要がある.例えば,ディジタル家電,自動車などに関しては,グローバルな競争環境,サプライチェーンとロジスティックス,貿易摩擦などの観点からグローバル生産が適しているが,東大阪における衛星プロジェクトや大田区における中小企業ネットワークなど,地域の活性化を目的としたローカルな生産も必要になる.
以上のように生産システムに関連する問題は,非常に多岐にわたり,学際的な幅広い分野の技術者,研究者が情報交換しながら,グローバルな競争環境の下で,日本の「ものづくり」産業が生き残るための新しい方向性を探っていく必要がある.
生産システム部門は,このような幅広い知識と経験をもつ技術者および研究者の人的ネットワークをつくり,相互の情報交換を行う場を提供するとともに,共同で問題の解決法を考えていくようにしたいと考えております.ぜひ部門内外の皆様のご協力をお願いいたします.
2007年度(85期)生産システム部門長 杉村延広(大阪府立大学)