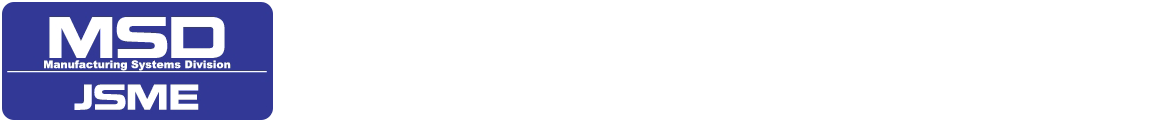83期部門長挨拶 「大いなる生産システム部門への期待」
生産システムが,manufacturing systemsなのかproduction systemsなのかについては,1960年代に概念が成立して以来,多くの議論がなされてきました.また,その意味する内容についても多くの意見があります.従って生産システム部門とひと口に言っても,そこに含まれる研究開発領域は狭義から広義まで様々ですが,私はなるべく広くとろうと思っています.すなわち,マーケティングから商品企画といった製品設計の初期から,製品設計,生産設計を経る技術情報処理プロセス,設計管理,生産管理を含む管理情報処理プロセス,そこで決まるwhat,how to,how many,whenの情報をもとに実際のものづくりを行う製造プロセス,流通を経て製品がユーザに渡るプロセス,ユーザの下での製品のライフサイクルと製品の最後までを管理し処理するライフサイクル・プロセス,さらに要素技術の研究開発までも含む広大な領域を生産システムとして捉えたく思っています.これは最近の事例にも明らかなように,それぞれのプロセスが決して独立しておらず相互に深く関連することから,総合的な研究開発領域の必要性が求められていて,これが生産システム部門の役割だと思うからです.
部門運営の観点からは,こうした広い領域を対象にすると「広く浅く」「薄い」議論の場になってしまう懸念が生じます.製品設計や製造プロセス等については,他学会,他部門でより領域を限定して深化した議論の場を提供しようとしているところもあります.そうした場の必要性も感じていますが,同時に相互に関連する近接領域を総合的に捉える本部門の重要性も大いに主張したいと思っています.生産システムの各領域に共通した方法論,サイエンスが存在するのであれば,総合的観点は非常に重要になるはずです.
製品設計と,生産設備あるいは製造プロセスの2領域をみても,設備設計者からすると後者が対象製品なのですから同一の方法論が適用できることになります.そうすると,これまでに製品設計でいわれている頻繁な製品開発,リードタイム短縮,ライフサイクル設計,といった観点がそのまま生産設備や製造プロセスにも適用され得ます.特に設備更新やライン設計変更といった活動が特に関連すると思われますが,こうした工場のライフサイクル関連領域はこれまで本部門でも余り活発な議論がなされてきませんでしたが,今後は重要なテーマのひとつとなるでしょう.
CAD/CAMシステムや,生産シミュレータ,自動化技術と情報ネットワークといった情報及び計算機関連技術の発達は,ここ20~30年間で生産システムの各領域に大幅な活動・手順及び設備・システムの変更が行われてきました.この波は現在ではひと段落しているように思えますが,IT技術の流れは更に細やかでかつコンスタントな変更を要求しています.いわば生産システム全体のライフサイクル対応が求められている現在,全ての領域を通しての効率化,最適化のためにも生産システム部門の発展が望まれるところです.
2005年度(83期)生産システム部門長 荒井 栄司 (大阪大学)