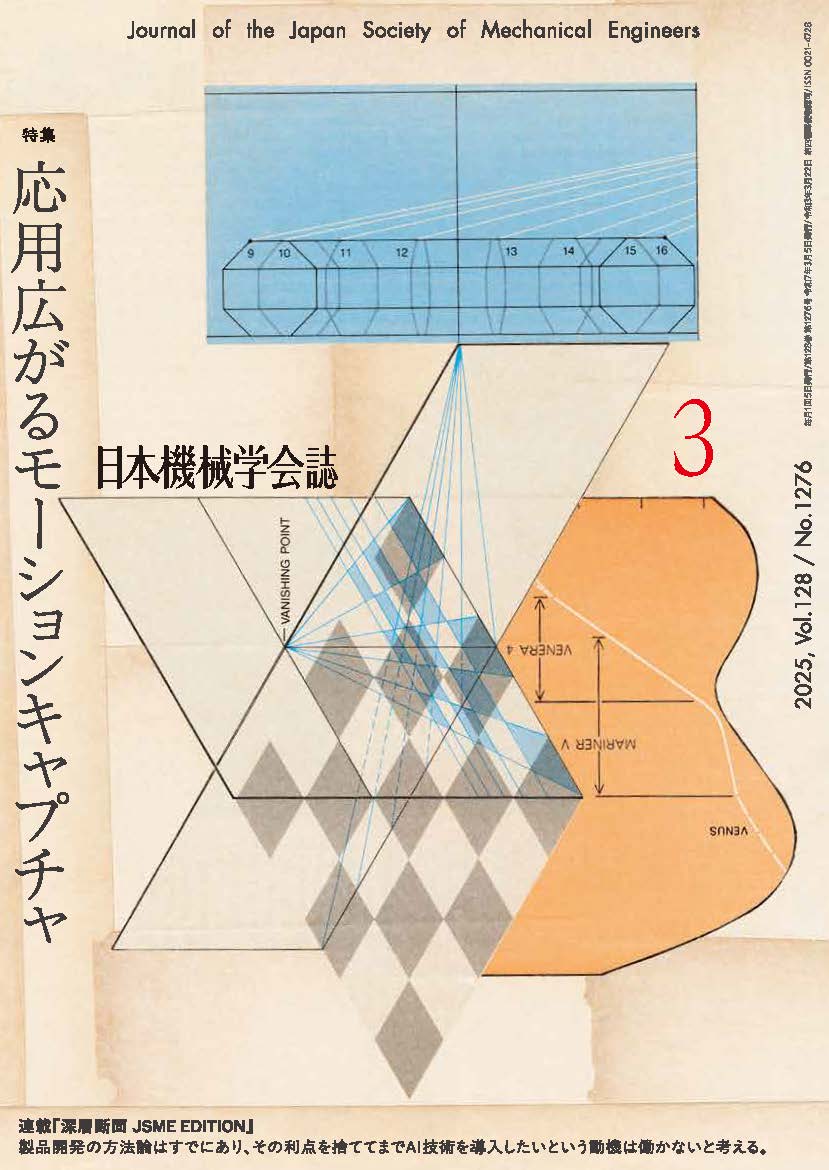No.1219, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1219-47/
大学時代の私は友人の間では不真面目として有名でした。修士学生時代にドイツの企業でインターン生として働いた際にも、「渡独してビアマイスターになるらしい」という噂がまことしやかに囁かれていたほどです。それも無理からぬことで、機械工学の基礎である「四力」はすべて単位を落として再履修しま…Read More
No.1218, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1218-38-2/
理想気体の状態変化 1. はじめに 本稿では,理想気体の状態変化について理解する。状態変化の基本的な考え方をまとめたうえで,代表的ないくつかの状態変化について,状態量の変化量や熱・仕事の移動量の計算方法を解説する。 2. 状態変化 作動物質がある状態から別の状態に変わるとき,その…Read More
No.1218, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1218-40/
産学連携において、企業側から大学・研究機関へアプローチすることはあっても、その逆のケースは珍しい。しかし、東北大学大学院工学研究科 堀切川 一男教授は、大学の教員でありながら地域の中小企業を訪問し“御用聞き”を行うことで、米ぬかを原料とした硬質多孔性炭素材料「RBセラミックス」や…Read More
No.1218, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1218-42/
No.1218, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1218-44/
Tips for Academic Publishing アクセプトに繋げる論文投稿&学術出版の豆知識 査読者からの質問や修正提案に対処するのは、ベテランの研究者にとっても手間がかかり気を遣う作業です。論文執筆に不慣れな研究者にとってはなおさらのことでしょう。 査読者から…Read More
No.1218, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1218-46-2/
生産性の指標である一人当たりGDPにおいて、日本は1995年から2000年にかけ世界2~3位であったが、現在は20位まで後退している。その理由と背景を探ってみよう。 一人当たりGDP 表1は一人当たりのGDP(名目、ドルベース)の推移とOECD諸国における順位を示したものである。…Read More
No.1217, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1217-47/
2018年度日本機械学会賞(論文) 「Strain distribution in the anterior cruciate ligament in response to anterior drawer force to the knee」 山川 学志、Richard E. …Read More
No.1217, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1217-48/
機械工学との関わりは機械工学科への配属に始まり、半世紀近くが経ちます。ここでは、特に材料力学の視点から取組みを振り返ってみようと思います。 今では技術も細分化され習得すべき技術の種類も多くなり(過ぎ?)、学生や教員も苦労されていると思います。私たちの学生時代には材料力学だと、材料…Read More
No.1217, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1217-34/
日本にはこんなすごい会社がある! 1885年、東京・日本橋で創業し、1909年からモーター製造・技術の世界に足を踏み入れたオリエンタルモーター。会社の設立は1950年。2020年で70周年を迎える、日本を代表するモーターメーカーの1社だ。 現在は、モーターとそれに組み合わせて使う…Read More
No.1217, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1217-36/
理想気体 1. はじめに 本稿では,熱力学で状態変化を考える際の作動物質として最もよく用いられる理想気体について理解する。理想気体がよく用いられる理由は,その状態方程式が非常にシンプルであるためであり,熱力学に関する様々な考察を行う際に理想気体を用いると状態変化の計算が簡単になり…Read More
No.1217, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1217-38/
No.1217, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1217-40/
企業ニーズドリブンを徹底した産総研の連携事業 研究成果と産業界との橋渡しを行うことで日本の産学連携推進を担う産業技術総合研究所(以下、産総研)。2015年度からの第4期中長期計画において企業ニーズを強く意識した施策を打ったことで、民間企業からの資金流入額を5年間で2倍以上に大きく…Read More
No.1217, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1217-42/
Tips for Academic Publishing アクセプトに繋げる論文投稿&学術出版の豆知識 ジャーナル投稿中の疑問を解決 Journal decision-making(ジャーナルの意思決定)にはさまざまなプロセスがあり、複数のscreening(審査)が行わ…Read More
No.1217, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1217-44/
―景気の動きをつかみ、景気の山谷を決める― これまで見てきたように景気を見る際の基本的な指標は三つある。内閣府のGDP統計、日本銀行の短観、内閣府の景気動向指数である。今回は景気動向指数と景気循環について説明する。景気動向指数は先行系列、一致系列、遅行系列の3系列があり、景気と同…Read More
No.1217, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1217-46/
子供の頃を思い出すと、バッタやトンボのヤゴを採って喜んでいるような少年でした。そんな私が機械工学に興味を持ったきっかけは、電子工作が好きな友人に誘われて一緒に工作をして遊んだことでした。気がつけば、「将来はロボットエンジニアになる!」という夢をもっていました。本稿では、そんな私の…Read More
No.1216, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1216-32/
技術のみちのり ー日本機械学会賞受賞技術の開発物語ー 2018年度学会賞(技術) 「高効率と低騒音を両立した換気扇用誘導モータの開発」 三菱電機(株) 換気扇用誘導モータのリニューアル 三菱電機(株)の中津川製作所では、換気扇などの空調設備を製造している。これまで5~10年おきに…Read More
No.1216, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1216-34/
化学工業などの基礎素材型産業や、製缶業や溶接業などの金属加工業が盛んな福島県いわき市。もともとは石炭産業で栄えた街だったが、炭鉱閉山以降は産業構造を転換させながら、多くの苦難を乗り越え、発展してきた。近年では、産業集積による優位性を生かし、バッテリーや風力発電などの産業振興にも力…Read More
No.1216, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1216-36/
No.1216, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1216-38/
Tips for Academic Publishing アクセプトに繋げる論文投稿&学術出版の豆知識 投稿した「あなたの論文」について行くことはできない以上、ジャーナルの意思決定を待っているしかない時間は長くつらいものです。本当に受理されただろうか、どこまで進んでいるの…Read More
No.1216, https://www.jsme.or.jp/kaisi/1216-40/
前回説明したように景気を見る際の基本的な指標は三つある。今回は、日本銀行の短観を取りあげる。短観は企業経営者が自社の業況や設備・雇用などをどのようにみているかを調査するもので、そのうち大企業製造業の業況判断指数が最も注目される。大企業の製造業は景気に敏感と言われているからであるが…Read More