- 開催日:2011年10月31日(月)
- 時間: 10:00-17:10
- 会場: 首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス (秋葉原ダイビル12階)
ものづくりが価格競争に陥らないためには,ユーザーの感性や心理を的確にとらえ,期待を超える魅力的な製品やサービスを打ち出す必要があります.しかし,魅力を感じる人の感性や心理は,主観的でとらえどころがなく,設計指針の意思決定や代替案の評価が属人的,恣意的になされることも希ではありません.
本講習会では,「魅力」を論理的に設計するために役立つ考え方や方法論について紹介し手頂きました.具体的には,多様な顧客の感性をいかに定量的,構造的に把握するか,感性的な魅力をどの様に管理して製品開発に展開するか,魅力の形成において重要なファクターである期待や不安を製品開発の中にいかに取り込むか,安心・快適・わくわく感をどの様に計測するか,魅力的な製品・サービスを提供するビジネスチャンスをいかに発見するかについて,各方面の専門家の視点から解説して頂きました.さらに,化粧品から自動車までの幅広い製品ジャンルにおける魅力の設計の実践例を紹介して頂きました.

何を魅力に感じるかは,個人の感性に依るところが大きい.感性は個人によって異なり,成熟化・国際化が進む今日においてはその多様性のすそ野は広がりつつある.さらに,個人の感性は,新しい情報や経験によって変化しうる.言い換えれば,外在化していない感性が潜在する.
本講演では,なぜ,今,魅力の設計なのかについての背景を概観したのち,感性の多様性を的確に捉える方法と,その情報を利用して潜在的な感性を抽出する方法について解説した.
- 東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻 講師
- 柳澤 秀吉

従来の品質管理では難しかった「感性的な魅力」の管理について,すでに10 年間の実務で成果をあげているPerceived Quality の乗用車開発への適用事例を取り上げ,その具体的な方法論及び仕組みについてご紹介頂いた.さらに,品質管理分野に於ける位置付けと今後の発展性についても解説して頂いた.
- 日産自動車㈱ デザイン本部
- パーシブド・クオリティ部 シニアスタッフ
- 片岡 篤 氏

魅力とは期待以上への予感や予測を指す.未来に起きるであろう事を意識しはじめた瞬間から,不安という心の動きにスイッチが入る.魅力は常に心理的に不安な要素を包含し,同時に意外性を期待している.魅力を紡ぎ出す新しいデザイン理論Expectology(期待学)の論理と製品開発等における実践的な応用性について紹介頂いた.
- 東京大学 デザインイノベーション社会連携講座 特任教授
- トライポッド・デザイン株式会社 代表
- 中川 聰 氏

安心感・快適感・わくわく感は,物質的な豊かさではなく精神的な豊かさを求める21 世紀の社会の新しいパラダイムにおいて極めて重要であると考えられる.しかし,それを定量的に計測しようという試みはあまり多くない.今回は,インタラクティブシステムのわくわく感を,アンケートや生体信号を利用して計測しようとした研究事例や,さらに人をわくわくさせる「かわいい人工物」の研究事例について紹介頂いた.
- 芝浦工業大学 工学部 情報工学科 教授
- 大倉 典子 氏

化粧品は社会学的,人文学的,さらには自然学的な側面をもつ文化的製品である.多面的な中,本講演では皮膚科学的魅力についてホメオスタシスの維持・逸脱の観点から老化と関連づけて論じて頂いた.特に顔面の色素沈着の存在は美学的に忌み嫌われる現象であり,本非均一性に対する考え方を解説頂いた.
- シャネル リサーチ&テクノロジー日本研究所 所長
- 安藤 信裕 氏

2000 年頃から筆者らが取り組んできたチャンス発見学とそのビジネス適用事例を起点として紹介し,さらに近年,独自のデータ可視化手法を取り入れながらビジネスシナリオの提案と評価をやりあう会話の場「イノベーションゲーム」とその導入事例を挙げてご説明頂いた.チャンス発見を要する組織活動に携わる人々のコミュニケーションにとって適度な衝突と遊び心が必要であることを解説頂いた.
- 東京大学 大学院工学系研究科システム創成学専攻 教授
- 大澤 幸生
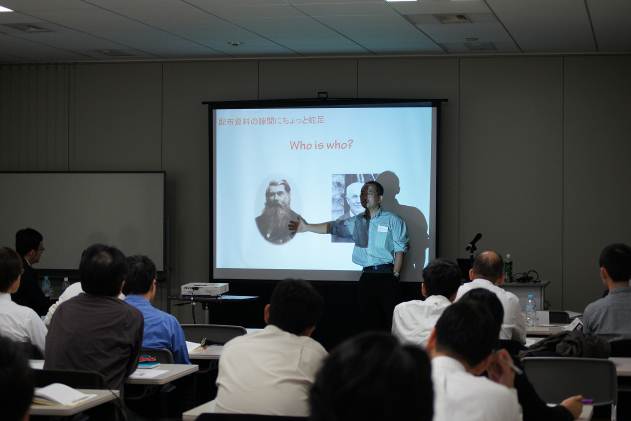
- 受講者:
- 48名(他に講師・事務局を入れて,合計58 名)
- 所属別:
- 企業29 名,大学・研究機関13名,不明6名
- 会員種別:
- 特2名,正13名,学2名,協賛12名, 外14名,外学5名
参加の目的
- 業務に生かすため:26名
- 業務の幅を広げるため:22名
- その他:4名(具体的に 論文の参考のため,学習の為 )
役に立ったか
- 非常に有意義であった.:23名
- どちらからといえば有意義であった.:21名
- あまりためにならなかった.:0名
今後の講習会に
- ぜひ参加したい.:11名
- 内容次第で参加したい.:34名
- 参加しないと思う.:0名
今後の希望テーマ
- 生体信号と心理測定
- ロボットのビジネス化(サービスロボットなど)
- 感性に対する国民性の特徴(好みや考え方の紹介)
- 想定外を想定できるリスク管理法
- 違和感からイノベーションアイデアの発見法
- 次回も同様のタイトルでより深いものを御願いしたい.
- システムデザイン,商品設計と顧客をつなぐ全ての共通概念
- 品質工学と感性品質の関係を深く掘り下げた内容のもの
- もう少し事例紹介を詳しくして欲しい
- 概論として良く分かったので具体的な内容の講義を希望します.
ご意見
"モノづくりの価値として『魅力』をクローズアップし,活かすことが重要との認識を強化できた.チャンス発見の為のツールも有効と思われるので取り入れたい.
企画者の所感
今回,初めての内容の講習会として,魅力の設計というチャレンジングなテーマを取り上げた.蓋を開けてみると,参加者がほぼ定員となり,6割程度が産業界からの参加者であることから関心の高さが伺えた.また,今回,いくつかの学会に新たに協賛をお願いし,機械学会以外の学会員の参加者も多かった.講師陣としては,大学から3件,デザイナーから1件,産業界から2件と,やや大学の比率が多かったものの各講演とも活発な質疑がなされた.産業界からは,副題にもあるように,自動車と化粧品というあえて大きく異なる分野の方に講演をお願いした.これは,インダストリアルデザイナーの草分け的存在であるレイモンド・ローウィの著書「口紅から機関車まで」から着想した.デザインには対象に依存しない共通的な考えや方法がある,という意味だと筆者は解釈している.今回の講習会でも,それぞれ分野としては異なる講師の方々であったが,考え方や方法の点でいくつか共通する点が見られた点が興味深かった.設計やデザインと同様に,「魅力」には分野を横串にするなにか共通性があるのかもしれない.今回の講習会だけでは,それが何なのかはっきりとは見いだせていないが,分野を超えた議論の場の重要性を感じた.
以上
