4.100周年記念講演会を終えて
組織委員長 谷下 一夫
慶應義塾大学理工学部
1986年にバイオエンジニアリング委員会(翌年部門に移行)が設置されて以来、日本機械学会におけるバイオエンジニアリング部門は機械工学の新分野の開拓に顕著な貢献をして来たと言えよう。現在設置されている部門の半数以上で、取り扱うテーマとして生体関連のものが含まれている。このような結果になったことの理由の一つはこれまで10年余りのバイオエンジニアリング部門での活発な研究発表、討論や啓蒙活動があったからで、それらが従来分野の研究者の意欲を刺激したことは否めないだろう。さらに来年は元部門長の林紘三郎先生が主催されるバイオメカニクスの世界会議が札幌で開催される。そのような状況の下で、本年が日本機械学会の100周年をお祝いするという年になり、我々バイオエンジニアリング部門としても、機械工学の中の新分野の発展を祝うと同時にこれからの21世紀の社会でのバイオエンジニアリングの役割の重要性を認識しようという趣旨で、国際会議を行うこととし、土屋先生が名誉大会長、筆者が組織委員長を務めさせて頂いた。会議の運営組織に関しては、すでに部門報でご報告してあるので、省略させて頂く。
国際会議はInternational Conference on New Frontiers in Biomechanical Engineeringと言う名称で、本年7月18日から19日の二日間、有楽町駅前の東京国際フォーラムで開催された。146件の発表で、発表者(共著者を含む)の延べ人数は395名であった。海外からは、チェコ、フランス、ドイツ、インド、イラン、イタリア、メキシコ、中国、ポーランド、シンガポール、スイス、オランダ、英国、米国からの発表があり、日本を含めて、16カ国の参加による国際会議となった。招待講演として、以下のような20名の世界的に著名な方から講演をして頂いた。Prof. L. V. McIntire (Rice University, U.S.A.), Prof. R. M. Nerem (Georgia Institute of Technology, U.S.A.), Prof. Peter D. Richardson (Brown University, U.S.A.), Prof. Jean-Jacques Meister (Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, the Swiss Confederation), Dr. Nikolaos Stergiopulos (Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, the Swiss Confederation), Prof. Janusz Kajzer (Nagoya University, Japan), Dr. Tetsuya Tateishi (National Institute for Advanced Interdisciplinary Research, Japan), Prof. J. C. Chato (Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.), Prof. Boris Rubinsky (Univ. of California, Berkeley, U.S.A.), Prof. Van C. Mow (Columbia University, U.S.A.), Prof. W. Michael Lai (Columbia University, U.S.A.), Dr. Kai-Nan An (Mayo Clinic, U.S.A.), Dr. James C. H. Goh (The National University of Singapore, Singapore), Emeritus Prof. Duncan Dowson (The University of Leeds, UK), Prof. Tadashi Sasada (Chiba Institute of Technology, Japan), Mr. Georg Panol (The Milton S. Hershey Medical Center, U.S.A.), Prof. Dr. Ing Dieter Liepsch (Fachhochschule Munich, Germany), Prof. Roger D. Kamm (Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.), Prof. Timothy J. Pedley (University of Cambridge, UK), Prof. Morton H. Friedman (Ohio State University, U.S.A.)。これらの先生方はバイオメカニクスやASMEのバイオエンジにリアリング部門などでお馴染みの方ばかりであるが、超多忙のところを強烈な東京の夏さなかに来て頂くことができた。これも部門や組織委員会の先生方のご尽力の結果であり、ニュースレターの紙面をお借りして改めて感謝申し上げる。形式的には特別講演と基調講演に分けたが、基調講演が他の講演と重なり、プログラムの組み方に多少不備があり参加された方にご迷惑をお掛けしたことをお詫びする。時間がゆるしたならば、同時に走る講演会場の数を減らして、開催日数を延長させた方が、色々な発表を聞けてよかったのかもしれない。
一般講演は、ほとんどオーガナイズドセッションの形式であったが、セッション数はポスターを含めて12件であった。ポスターセッションを設けるかどうかかなり組織委員会で議論になったのだが、最終的に東工大の清水優史先生の案で、大きな部屋をポスター会場として、コーヒーサービスや討論用の椅子とテーブルを置くことにしたが、これは大成功であった。ほとんどの参加者がポスター会場に来て下さり、コーヒーを飲みながらの熱心な討論の輪があちこちに見られた。最終的な参加者数は215名であった。国際会議の規模としては小さなものであったが、内容的にはかなり充実したものになったと思っている。この国際会議がさらにこれからの生物機械工学の発展に少しでもお役に立つようなことになれば、お世話させて頂いた立場としてこの上無い喜びである。最後に、バイオエンジニアリング部門として始めての国際会議を無事開催出来たのは、これまで過去3年間に渉る部門長や部門の先生方並びにアドバイザリーボードと組織委員会の先生方のご協力のお陰であり、心から感謝申し上げたい。尚、まだプロシーデイングが多少残っているので、購入ご希望の方は筆者又はバイオエンジニアリング部門事務局までお問い合わせ頂きたい。
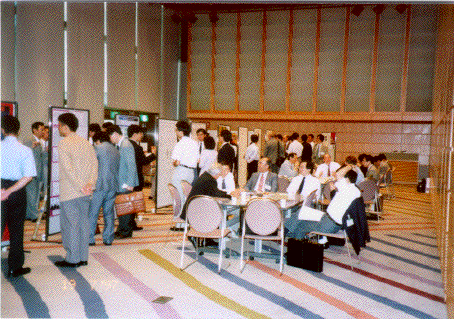
写真 ポスター会場にて
All Rights Reserved, Copyright (C) 1998, The Japan Society of Mechanical Engineers.
Bioengineering Division