7.研究室紹介
放射線医学総合研究所重粒子治療センター 重粒子物理・工学研究部
宮原 信幸
放射線医学総合研究所は昭和32年の設立以来、放射線による人体の障害と
その予防・診断・治療および放射線の医学利用に関する調査研究ならびにこれ
らに従事する技術者の養成訓練を行っている。当研究部では、高齢化社会の到
来とともにがんによる死亡率が増加していることから加速器(HIMAC:Heavy
Ion Medical Accelerator in Chiba )を用いたがん治療装置の開発研究を行っ
ている。
現在までに知られている難病のうち、がんはもっともよく知られている疾病
である。しかしながら、有効な予防手法は現在までのところ知られておらず、
早期発見、早期治療以外に有効な手だてはない。がんの治療としては、外科的
治療(手術による患部の除去)、化学療法(抗がん剤の投与)、放射線治療
(放射線照射によるがん細胞の制御)が主なものである。このうち、放射線治
療はラジオアイソトープ、X線、中性子線、陽子線等が用いられており、局所
のがん治療に適しているとともに、臓器の機能を損なうことなくまた、重篤な
副作用の心配なく治療を行うことができ、他の手法に比較してQOLの高い治
療であると考えられる。当研究所では、従来の放射線に比較してより優れた重
粒子線(炭素ビーム)を開発し臨床試行を行っている。重粒子線は従来の放射
線に比較して以下のような優れた点が利用できると考えられている。
(1)線量分布が圧倒的に優れている。
X線、γ線、速中性子線の体内での線量分布は入射表面から指数関数的に減
少し、がん病巣を含む標的領域の線量はそこにいたるまでの正常組織に与えら
れる線量よりも低く、また、標的領域通過後の正常組織に対しても線量の寄与
が続く。他方、重粒子線は粒子の種類とエネルギーによってその到達距離が決
まり、最終到達点でブラッグピークと呼ばれる線量ピークを形成する。このピー
ク以降は1次重粒子線の寄与は無く、わずかな2次粒子線の寄与のみである。
(図1)従って、標的領域にのみ線量を集中することが出来る。
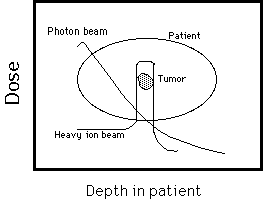
図1 各種放射線における深部線量分布
(2)生物学的効果が高い
放射線に対す生物の反応は、放射線の種類により異なっている。重粒子線は、
同じ線量に対する細胞致死率の起こる生物学的効果がX線やγ線に比較して約
3倍ほど高い。これは、重粒子線の飛程終端においてビーム進行長さあたりの
線エネルギー付与率(LET)が極めて大きいためである。
(3)酸素効果比が低い
X線やγ線の場合、腫瘍内の酸素が欠乏している場合には生物学的効果が著
しくて以下する。しかしながら、重粒子線の場合には高LETであるために生
物学的効果が腫瘍内酸素濃度にほとんど依存しない。
上記のような特性を有する重粒子線を有効に治療に利用するために図2に示
す重粒子線がん治療装置の建設を1994に完成した。現在は、頭頚部、胸部、子
宮、肝、前立腺等の腫瘍を主な適応として臨床試行を行っており、1996年3月
の時点では104名の治療を行い、経過を観察している。今後は、重粒子線治療
の適用範囲を拡大し、臨床データを蓄積してゆくとともに2次ビームを用いた
治療・診断ならびに放射光を用いた診断機器の開発を行う予定である。
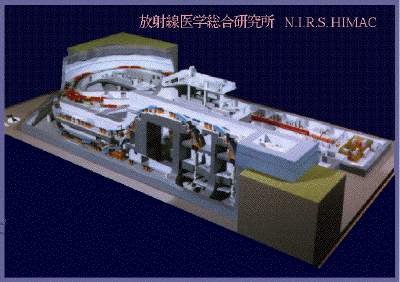
図2 重粒子線がん治療装置
All Rights Reserved, Copyright (C) 1996, The Japan Society of Mechanical Engineers.
Bioengineering Division
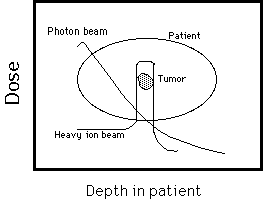
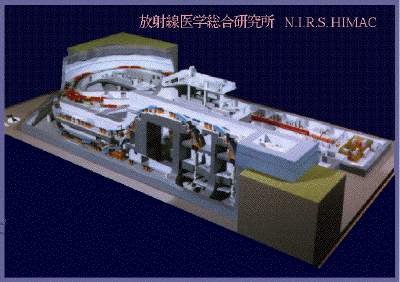
目次へ