はじめに
一昔前までは福祉用具(機器)というと、手足の切断を受けた人が使う義肢(義 手や義足)や、手足の麻痺や身体に変形のある人が使う装具、そして車椅子と考 えられてきたような感があった。これら以外にも当初から視覚障害者や聴覚障害 者に対するものを始めとして多様な用具が開発されてきていたが、いずれも、社 会の少数派である身体障害者のためのものとされてきた。近年、高齢者の急増に よる介護者の不足から自立支援機器や介護を支援する機器などが注目されるよう になり、その範囲が広がるとともに、通産省の指導の下、これまであまり関心を 持たなかったように見えていた大企業なども参入を始めたようである。本年の 10月に東京の晴海で行われた第22回国際保健福祉機器展には10万人を越え る参加者があったともいわれ、福祉用具が一つの産業分野として確立される日も 近いといわれている。しかし、これまで大量生産されてきた一般的な消費財とは 異なる点が多いことから、研究開発と実用化のポイントを絞りきれないといわれ ることが多い。ここでは、高齢社会において福祉用具を必要とするようになる背景をいくつか のデータとともに紹介し、つづいて筆者らが開発したインテリジェント大腿義足 とその実用化を例にとり、福祉用具の研究開発と実用化の問題点を考察する。
高齢社会の到来、障害者と福祉用具のニーズとシーズ
高齢障害者と障害者は動作やコミュニケーションに障害が生ずる点では同様の障 害を持つと見ることができる場合もあることから、研究の対象としたり福祉機器 を開発する場合に区別せずに扱うことがある。行政上は高齢による身体の不自由 と身体障害は区分されており、取扱いが異なる。身体障害者は身体障害者手帳を 所持しているものに限定され、肢体障害、視覚障害、聴覚障害、および、内部障 害に区分され、総数で300万人を超えるが、そのうち重度の障害のために福祉 機器を必要とするものは数10万人と考えられている。近年法律が改正され、従 来の身体障害者福祉法は精神障害者も含めた障害者法となった。しばしば取り上げられるているように、西暦2025年には日本の人口の4分 の1は65才以上の高齢者になるといわれている。もちろん、その年になって突 然変化するわけではなく、それまでに徐々に変化していくわけで、現状では約 14%、2000年には17%、2010年には21%になると推計されてい る。このように増加してもすべてが健康で介助を必要としない高齢者であれば福 祉機器の開発ブームは起こらないが、図1のように要介護高齢者が急増すること が予想されており、その数は2010年には236万人となって、1990年の 2倍以上になるといわれている。また、そのうちの70%以上が在宅の要介護者 になるともいわれている。いっぽう、労働人口は1995年を境に減少するとい われており、介護者の不足が懸念されている。同時に介護する側の者が高齢にな るといわれており、すでにそのようなケースがしばしば見られるようになってき ている。政府の定めた高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン、後に新 ゴールドプラン)によるとホームヘルパーやデイサービスの充実など、人手によ る支援の強化を中心としているようにみえるが、エンジニアとしては不足する人 手をいかにして補うかについての方策は不十分であるように感じられる。機器の 支援により寝たきりになることを防止するとともに、自立を促進し、人手の不足 分を機器によって補い、介護の効率をあげることが必要であると発想するのは当 然であろう。
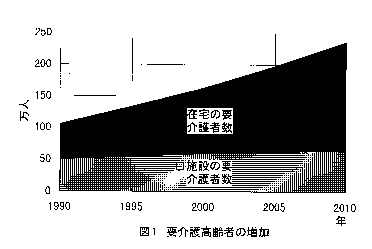
介助者にとって最も負担が多い項目は入浴、排泄、食事の介助であるといわれ ている。また、介助をされるものにとってもこれらは可能な限り自立したいと 願っていることであるが、これらをさらに分析すると、被介助者を移動させると いうことが最も大きな負担であるとされている。高齢者を対象とする研究による と、いすやベッドの生活をしている西洋の高齢者にとっては、立ち上がり動作が 最も負担が大きく、立ち上がってしまえば、歩行や移動はそれほど大きな負担と はならないといわれている。畳の上に寝る習慣を持つ日本人には、さらに厳しい 負担となることは容易に想像され、阪神大震災直後に体育館などの起き上りの手 掛かりがない避難所で、寝たきりになってしまった高齢者が多かったことなどか らも、このことは容易に理解することができる。この点はこれまでの福祉機器の 見落としていた部分であったと考えられる。移動の補助具としての車椅子や歩行 車、杖などが生産されてきたが、家屋改造で最も多い工事が手すりの取り付けで あることや、起き上がり補助いすが注目されるようになってきていることなど も、この事を裏付けている。
図2のような移動の困難な人を抱き上げて移動を補助するリフトを例にとる と、被介護者からみると基本要素としてのリフト機能と、身体に接触する適合要 素であるスリング(ベルトや布の場合が多い)に分かれる。また、介護者から見 ると、同様に基本要素であるリフト機能と、持ち上げる操作をする機器操作部に 分かれる。これまで我が国では福祉機器を開発する場合、基本要素であるリフト 部が最も重要視され、開発に力がいれられてきた。しかし、使用する現場から は、付属するスリングや操作部が適当でないためにリフト全体が不適確な製品で あるかのように評価されることがしばしば見られた。最近になってようやくこの ような見方が適切ではなく、マン−マシンインタフェース部分の重要性が認識さ れるようになってきたが、従来の概念におけるマン−マシンインタフェースの評 価方法が適用できないことが多く、明確な方法論が提示されないまま、経験を基 にした判断と指導が行われている。経験のないものにとっては、何が評価を左右 するポイントであるかについてわからない場合でも、微妙な差が大きな差につな がることがあるが、定量的な説明ができないことが多く、何等かの明確な客観的 評価方法が提示されるならば、福祉機器の普及には大いに参考になるものと考え られる。
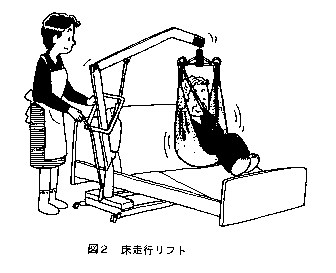
大きなプロジェクトで行われてきた福祉機器開発のいくつかでは、この基本要 素と適合要素を明確に区分せずに着手されたと見られるものがあり、基本要素の みの開発で終了し、実用に供することができなかったものもあるようである。前 述のように適合要素部分の開発と評価には定型の方法論が確立されておらず、研 究者にその重要性が認識されてこなかったように考えられる。これまでの長い経 過から、基本要素部分に関してはかなりの種類のものが開発され、製品化されて きているようであるので、今後は適合要素部分の開発と研究に重点を移す時期に なっているように感じる。そのためには、高齢者や障害者を含む、ひとの基本的 な動作特性を解明するとともに、これまでの方法論とは異なった手法を開発する ことが必要となってきているものと考えられる。次節では、筆者らが開発してき た大腿義足の膝継手を例として、機器の研究開発と実用化を考えてみたい。
インテリジェント大腿義足の開発と実用化
この研究開発は筆者らが1978年に開始し、1993年になってようやく製 品化されて義足使用者に使用可能となったものである。義足の制御に初めてメカ トロニクスを応用したもので、研究段階から実用化へのプロセスを経たものとし て、福祉用具の研究と開発の参考にしていただければ幸いである。- 義足におけるマン−マシンシステムと従来の義足の問題点
手足の切断を受けた下肢切断者が使用する義肢は、その欠損部を補い、義足使 用者と一体となって目的の動作を行うマン−マシンシステムを構成する。そのた め、独立した機器を人が制御する一般のマン−マシンシステムとは異なった取扱 いが必要となる。例えば、体重を支え、感覚とアクチュエータとして動作する神 経−筋−骨格系としての脚を失い、その代替物としての義足を使用する場合に は、人の持つ動作特性と義足の持つ動作特性が融合した、新しいマン−マシンシ ステムとしての特性が形成されると考えることができる。それでは、この人−義 足系システムではどのような歩行パターンを目指すのがよいのであろうか。も し、そのような歩行パターンが理論的に得られたものとして、それが健常者のそ れと異なるとすると、それを切断者が望むものであろうか。リハビリテーション の現場では、義足については健常者の歩行パターンに近づけることが目標とさ れ、歩行訓練も同様の目標を設定している。したがって、義足を設計するに際し ても、常に健常者の歩行に近づくことができることが目標とされてきた。
さて、従来の義足はすべて機械要素から構成されてきた。これらの多くは第2 次世界大戦後の戦傷者対策としてアメリカを中心に開発されたもので、簡単なも のでは何等制御要素を持たないものから、空気圧や油圧のダンパ的なものまで、 さまざまな研究開発がなされてきた。これら、メカニカルな要素を用いたもので は平地を一定の速度で歩行するときの歩行特性にあわせたものが大半で、歩行速 度の大幅な変化や坂道や階段での歩行に適応的に特性を変化させることはできな かった。これらの機構には、それぞれの切断者の歩行能力にあわせるための調整 機構があり、経験的にはいろいろな歩行速度や切断者の歩行リズムにあわせて調 節を変えることによって適合させることができることがわかっていた。しかし、 この調節を歩行中に行うことができなかったとともに、これらは制御という概念 を明確に導入したものではなく、トライアンドエラーにより設計されたものと考 えられた。そこで、義足歩行を制御の対象として捉え、その改善を試みた。義足 の制御というと直感的には動力義足の導入が考えられるが、小型大容量のエネル ギー源を入手できる可能性が当面の間ないことが明らかであったので、当初から 動力化をめざさず、それまで使用されてきた調整機構を制御の対象とすることに よる高精度化を行うこととした。
- 大腿義足の制御
義足歩行には、図2のように義足が床に接している立脚相と、床から離れて振動 している遊脚相がある。立脚相は歩行の安定性に、遊脚相は歩行速度や歩行のリ ズムなどに関係するといわれている。立脚相でなんらかの制御を行う場合は、切 断者の体重を考慮しなければならず、大出力のアクチュエータと大きなエネル ギー源を必要とする。いっぽう、遊脚相では義足部分の振動の制御のみでよいの で、小さなエネルギーしか必要としない。これらのことから、遊脚相を制御対象 とすることとなったが、入力値と目標値を何にするかを決めなければならない。 大腿義足では切断された断端と義足の大腿部であるソケットで接続され断端で振 られるが、膝より下の下腿部は膝に相当するヒンジジョイントで大腿部に接続さ れ、遊脚相で振動をおこなう。対象としてとりあげた従来型の義足では、図3の ように膝のジョイント部にダンパのような空気圧シリンダがとりつけられてい る。そこで、切断者の歩行時の大腿部の振動を入力とし、下腿部の大腿部に対す る相対的振動の角変位を健常者のそれに近づけることを目標として、この空気圧 シリンダのバルブを制御対象とすることとした。シミュレーションプログラム上 ではバルブの比例制御を振動中に行い、よい結果が得られる可能性が示唆されて いたが、シリンダの内圧が高くなっている時に動作することが可能な小型で高速 のアクチュエータが得られなかったことから、振動中にバルブの全開と全閉を高 速で繰り返すことによって同等の結果を得ることができるようにハードウェアと ソフトウェアを改造した。この制御方法によって平地歩行で速度を変化させた場 合に、広い速度範囲で目標値である健常者の膝の屈曲角変位に近似させることが できることを確認した。さらに、坂道を歩行した場合、階段を降りる場合などに ついても、制御データを検討し、歩行実験を行った。
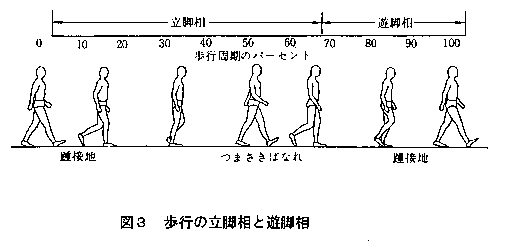
- インテリジェント大腿義足の実用化
前述の制御問題を解いて制御データを得るためには、多くのプロセスを経るとと もに、大規模な歩行分析システムや、一定レベル以上のコンピュータ(当時とし ては)が必要となるなど、義足の現場の状況を考慮すると高度すぎる内容と判断 された。そこで、義足を扱っている現場にも受け入れられる範囲内での義足の高 機能化を目指すこととなった。そこで、健常者の膝の角変位をシミュレートする よりは、義足使用者や歩行訓練を行う理学療法士や義足を製作する義肢装具士が 感覚的によい歩行と感じられるように、ティーチング・プレイバック制御の概念 を取り入れ、広い範囲での歩行速度の変化のみに対応できるようなシステムを構 築することとなった。先に述べたシミュレーションを目的とするシステムに比較 して、図4のように制御データ決定のプロセスが簡略化され、義足製作や訓練の 現場で受け入れられる見込みが立てられるようになってきた。
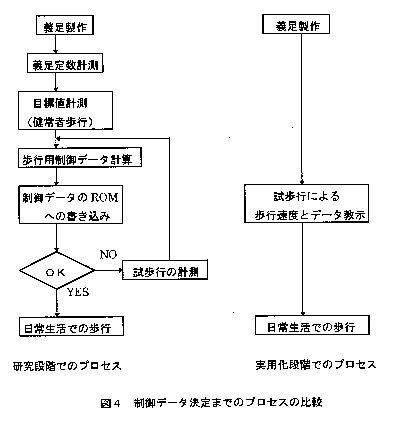
このシステムでは、遊脚相の制御を行うに際して、歩行速度を3段階に分割し て、各々の速度に対応する空気圧シリンダの弁開度を小型のリニアステッピング モータを用いて、試歩行時に教示する。日常生活での歩行においては、歩行の1 サイクルの時間が歩行速度を代表するものと考え、その速度に対して教示した弁 開度から一致するものを選択し、遊脚相開始前にその弁開度に設定する方式とし た。本方式では遊脚相中に弁開度を変化させることによる制御は行わないことと し、歩行速度が変化したときのみに弁開度を変化させる方式を採用したために、 アクチュエータの動作頻度が著しく減少し、小型の1次電池で約1年の使用がで きるようになり、図5のような製品として実用に供することが可能となった。

図5 インテリジェント大腿義足
- 実用化に際しての考察点
義足の実用化モデル開発の過程で、初期のシミュレーションモデルに対して残す べき機能と簡略化するべき機能の選択が問題となった。また、義足を製作し、義 足装着の訓練を行う現場の技術レベルも大きな判断要素となった。一方、シミュ レーションモデルでは義足を使用する切断者にどの程度のフレキシビリティがあ るかという点、義足使用者は何をどのように感じて評価をしているかという点、 そして、訓練の効果がどの程度得られるものかについての考察が加えられていな かったが、健常者でも自分の歩行時の姿を、側方から客観的に眺めたことがない ように、膝の屈曲角変位は、義足使用者にとって感覚的に捉えることができない 評価関数であり、それよりは、遊脚相のリズムが義足使用者の意図通りであるか どうかについて、よりセンシティブであることなどがわかってきた。これらにつ いて義足歩行の計測からわかったことは、下腿部が伸びて着地しようとするとき に、100分の2秒程度の遅れでも、感覚的にはリズムが悪く、意志通りの歩行 をすることができない義足であると判断できるが、遊脚相での膝の最大屈曲角度 については的確には判断できないということであった。訓練の効果や人のフレキ シビリティについては、義足が製品化され、多くの切断者に使われるようになっ て、義足使用者に開発者側やスタッフが改めて教えられた感がある。予想された 以上に速く歩行する切断者や、また、不可能と思われていた走行を行うものまで 現れてきた。走行といってもジョギング程度の速度ではあるが、空気圧シリンダ では制動が働くのが遅く、膝の後方への跳ね上がりを押さえることができないと 予想されてきた点を、巧みな断端の振りによってカバーしているのである。これ らの結果、義足を使用するための歩行訓練についても見直しが行われるようにな り、当センターでは活動度の高い切断者に対しては、新しい訓練プログラムが採 用されるようになった。